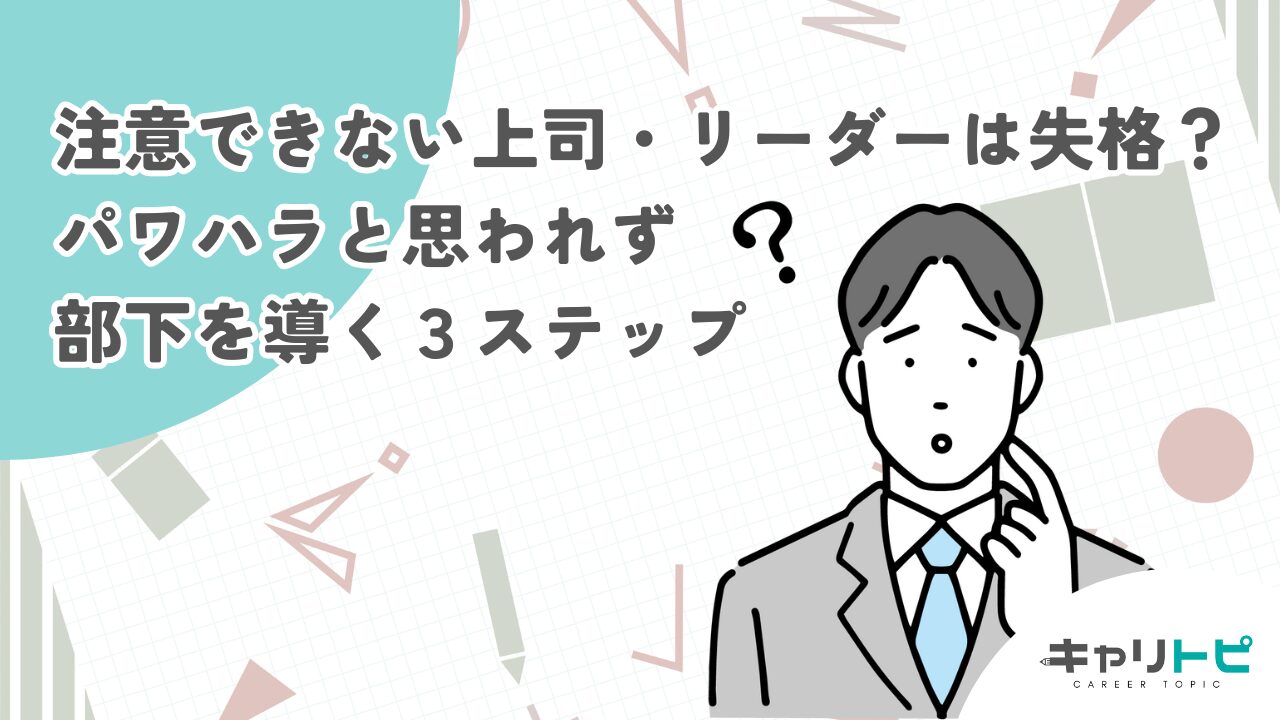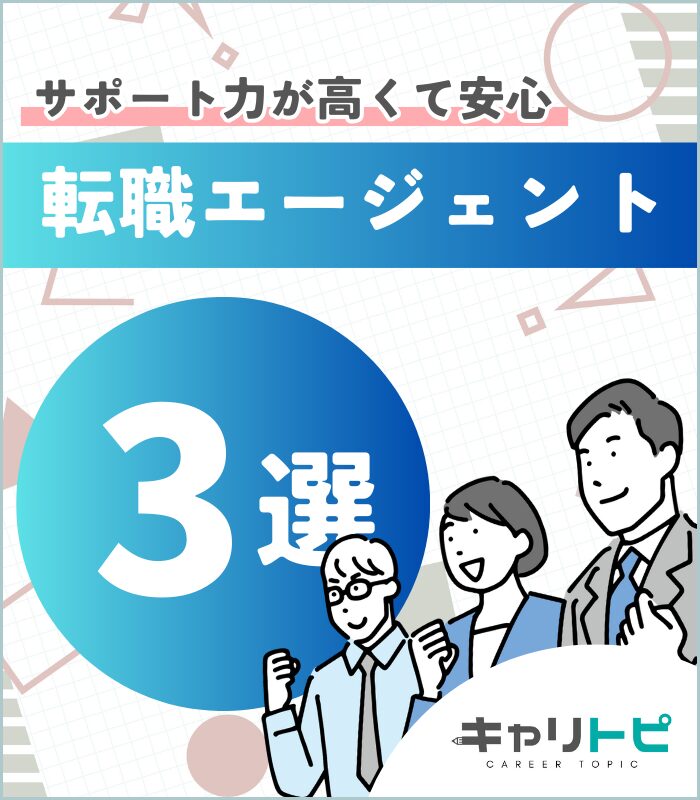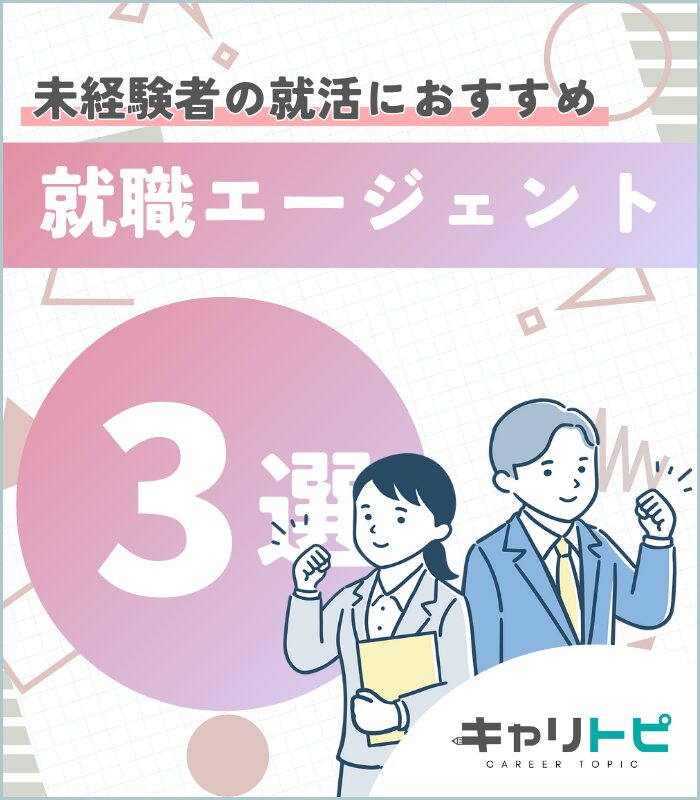「人に注意できないのは性格のせい?」
「若い子に注意しないリーダーは悪影響?」
「部下や若い子への注意や指導が難しい」というのは、多くの上司やリーダーが抱える悩みです。
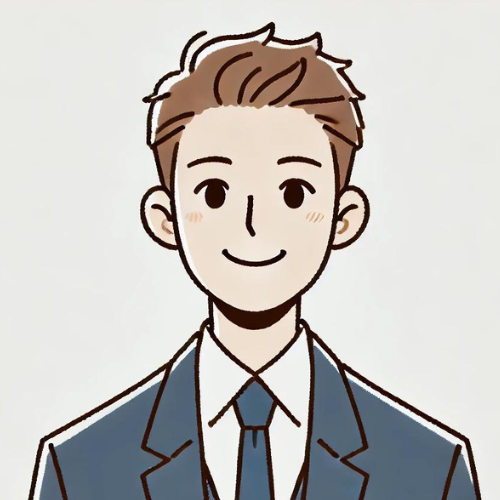
はじめまして。転職サポーターのゆうきです。
フリーターから就職した経験や転職経験、人事目線を活かして働き方や転職に関する記事を執筆しています。
この記事では、「注意できない上司・リーダーは失格か?」という視点で、注意しない心理や誰も注意しない職場の課題、若い子への接し方やあえて注意しない選択肢など、具体的な解決策をまとめました。
結論としては、パワハラと思われずに部下を導くには、伝え方や心理的な配慮、職場環境の工夫が重要です。
-
上司が部下に注意できない心理的な原因
-
注意しない行動が部下の成長に与える悪影響
-
パワハラと誤解されずに部下を指導する伝え方
-
部下との信頼関係を築きチームを育てる心構え
注意できない上司・リーダーが抱える悩みとは?心理と原因を解説
- 部下に嫌われるのが怖い|注意できない性格は変えられる?
- パワハラを恐れる注意しない上司の心理
- 誰も注意しない職場がチームに与える深刻な悪影響
- Z世代とのギャップ?若い子に注意しない上司になる理由
- 自分がやった方が早いと感じてしまう罠
- 指導の自信のなさが自己肯定感の低下とストレスに繋がる
部下に嫌われるのが怖い|注意できない性格は変えられる?
「部下に注意すると、嫌われてしまうかもしれない」。そう思うと、どうしても言葉が詰まってしまいます。特に、これまでプレイヤーとして人間関係を大切にしてきた方ほど、その傾向は強いかもしれません。

「人に注意できない性格」だと自分を責めてしまう人もいますが、これは必ずしも変えるべき短所ではありません。
その感情の根底には、相手を尊重し、チームの和を保ちたいという優しさがあります。
部下との関係性を壊したくない、職場の雰囲気を悪くしたくないという気持ちは、リーダーとして非常に大切な資質です。
問題なのは性格そのものではなく、注意する際の「方法」を知らないだけ、というケースがほとんどです。
相手に伝わる注意スキルを身につける
優しい言い方だけでは、部下に意図が伝わらず、同じミスが繰り返されてしまうことがあります。結果的に、あなたが手直しをすることになり、自分の業務時間が圧迫される悪循環に陥るのです。これでは、チーム全体の成長にもつながりません。
大切なのは、無理に厳しい性格になろうとすることではないです。性格を変えようとするのではなく、新しい「スキル」として、相手に伝わる注意の仕方を身につけるという視点を持ってみましょう。
成長のための贈り物(フィードバック)
例えば、注意を「攻撃」ではなく「成長のための贈り物(フィードバック)」と捉え直すのはいかがでしょうか。
部下の行動そのものではなく、その行動が引き起こす「事実」と「影響」を客観的に伝えるのです。そうすることで、感情的な対立を避け、部下自身に課題を認識してもらうことができます。
「人に注意できない」と感じるあなたの優しさは、部下との信頼関係を築く上で大きな武器になります。
パワハラを恐れる注意しない上司の心理
「この言い方は、パワハラだと思われないだろうか」。部下への注意をためらう最大の原因は、パワハラへの恐怖心かもしれません。
特に現代では、会社からもパワハラ防止の重要性を繰り返し伝えられており、指導する側が過度に萎縮してしまう状況が生まれています。

注意した結果、部下に深く落ち込まれたり、言い訳をされたりすると、指導への自信を失ってしまうこともあるでしょう。
部下との関係が悪化することや、最悪の場合、退職につながる事態を避けたいという気持ちも強く働きます。こうしたリスクを考えると、「見て見ぬふり」をする方が安全だと感じてしまうのです。
自己防衛の意識
この「注意しない上司」の心理には、自己防衛の意識が隠れています。問題を指摘してトラブルに巻き込まれるよりも、現状維持を選ぶ「事なかれ主義」とも言えます。
また、「きっと誰かが注意してくれるだろう」という責任回避の気持ちや、そもそも「どう注意すれば良いか分からない」というスキル不足や自信のなさが原因の場合もあります。
パワハラと正当な指導は全く違う
しかし、忘れてはならないのは、パワハラと正当な指導は全く違うという事実です。
パワハラは、感情に任せて人格を否定したり、相手を追い詰めたりする行為を指します。一方、正当な指導は、客観的な事実に基づいて、改善点を具体的に伝え、相手の成長を促すためのものです。
パワハラを恐れて必要な注意を怠ることは、短期的には波風を立てないかもしれません。しかし、長期的には部下の成長機会を奪い、チーム全体の規律を乱す原因となります。結果として、より大きな問題に発展するリスクを抱え込むことになるのです。
誰も注意しない職場がチームに与える深刻な悪影響
あなたが注意をためらうように、他の誰もが注意をしない職場は、一見すると平和に見えるかもしれません。しかし、その水面下では、チームを蝕む深刻な問題が静かに進行しています。
問題行動が放置される文化は、組織全体をゆっくりと衰退させていくのです。
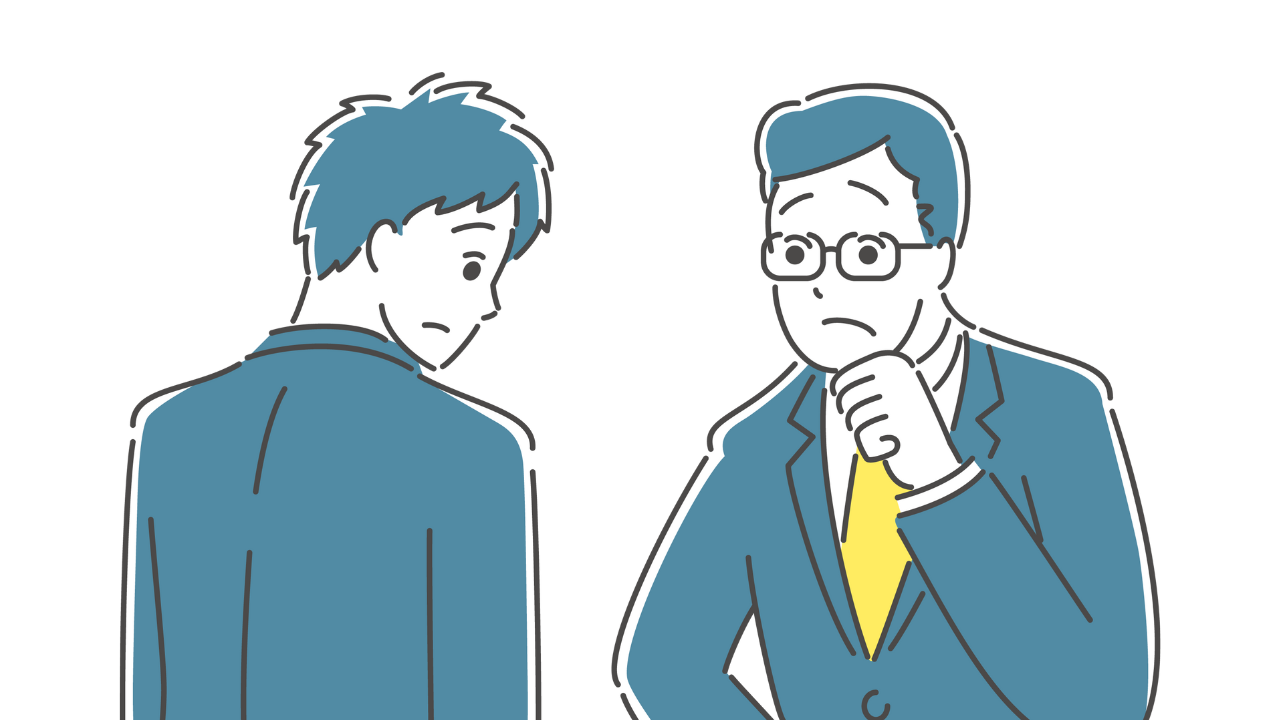
真面目に仕事に取り組んでいる社員が影響を受ける
まず、最も大きな影響を受けるのは、真面目に仕事に取り組んでいる社員たちです。
ミスやルール違反を見過ごされる環境では、「頑張っても意味がない」という不公平感が募ります。彼らのモチベーションは徐々に低下し、職場への貢献意欲も失われていくでしょう。結果的に、優秀な人材ほどその職場に見切りをつけ、離れていってしまうリスクが高まります。
チーム全体の生産性が著しく低下
次に、チーム全体の生産性が著しく低下します。注意されないため、同じミスが何度も繰り返され、そのたびに手戻りや修正作業が発生します。
あなたが個人のスキルでカバーし続けても、それは一時しのぎに過ぎません。チームとして学習する機会が失われ、組織全体のパフォーマンスは頭打ちになってしまいます。
部下自身の成長機会を奪う
さらに、部下自身の成長機会を奪うという側面も見逃せません。注意やフィードバックは、本人にとって自分の課題に気づき、改善するための貴重な機会です。
注意されない本人は「自分のやり方で問題ない」と誤った認識を持ち続け、成長が止まってしまいます。これは、愛情を持って部下の将来を考える上司の行動とは言えません。
コンプライアンス意識の低下
そして最も危険なのが、コンプライアンス意識の低下です。小さなルール違反が黙認される職場では、やがて「このくらいなら大丈夫だろう」という空気が蔓延します。
これがエスカレートすると、情報漏洩やハラスメントといった、企業の信頼を揺るがす重大な問題に発展する可能性も否定できません。
Z世代とのギャップ?若い子に注意しない上司になる理由
「最近の若い子の考えていることは、どうも理解できない」。Z世代と呼ばれる若い部下との間に、見えない壁を感じていませんか。
自分が新人だった頃の常識が通用せず、どう指導すればよいか分からなくなり、結果として「若い子に注意しない上司」になってしまうのは、よくある悩みです。

あなた自身が経験してきた「仕事は背中を見て盗め」「まずは自分でやってみろ」といった指導方法は、残念ながら今の若い世代には響きにくいかもしれません。
彼らが育ったのは、インターネットで検索すればすぐに答えが見つかる時代です。そのため、理由や目的が分からないまま行動することに強い抵抗を感じる傾向があります。
論理的で納得できる説明が必要
彼らが求めているのは、感情的な叱責ではなく、論理的で納得できる説明です。
なぜこの仕事が必要なのか、どんな目的があるのか。その業務をやり遂げることが、自分のどんな成長やスキルアップに繋がるのか。
こうした背景を丁寧に伝えることで、彼らは初めて「自分ごと」として仕事に前向きに取り組むようになります。
若い子に響く伝え方にアップデートしていく
また、「叱られる経験」が少ないのも彼らの特徴です。
そのため、良かれと思って熱く指導したつもりが、相手には「人格を否定された」と受け取られ、モチベーションを大きく下げてしまう危険性もあります。
最悪の場合、パワハラだと感じさせてしまい、離職につながる可能性もゼロではありません。
だからといって、何も注意しないのが正解というわけではありません。問題は「注意しない」という選択ではなく、「伝え方を知らない」という点にあります。「
若い子に注意しない」のではなく、「若い子に響く伝え方」にアップデートしていく必要があるのです。
客観的な事実とお願いをセットで話す
例えば、「なんで報告しなかったんだ」と詰問するのではなく、「報告がないと、次の工程で困る人が出てくるんだ。だから、まずは一言くれると助かるよ」と、行動が与える影響を具体的に伝えます。
あなたの感情ではなく、客観的な事実とお願いをセットで話すことで、相手も素直に受け入れやすくなります。
自分がやった方が早いと感じてしまう罠
「もういい、俺がやった方が早い」。部下の仕事ぶりを見て、ついそう感じてしまうことはありませんか。
特に、あなたのようにプレイヤーとして第一線で活躍してきた人ほど、この「自分でやった方が早い病」に陥りやすいものです。それは、あなたが優秀であることの裏返しでもあります。

この思考の背景には、いくつかの心理的な要因が隠されています。
自分の基準で仕事の質を判断してしまう「完璧主義」や、部下のミスでプロジェクトが遅延することへの「失敗への恐れ」。
そして、「状況を自分の管理下に置きたい」という無意識のコントロール欲求も関係しています。
短期的に見れば、あなたが手直しをすることで、確かに仕事は早く、質の高いものに仕上がるでしょう。しかし、その判断は、長期的に見るとチームとあなた自身の首を絞めることになります。
あなたが部下の仕事を取り上げてしまうと、部下はいつまで経っても失敗から学ぶ機会を得られず、成長できません。
その結果、部下は「どうせ最後は上司がやってくれる」と依存的になり、主体性を失っていきます。
あなたは「部下が頼りない」と嘆き、増え続ける業務に忙殺される。チーム全体の生産性は上がらず、優秀だったはずのあなたがボトルネックになってしまうという、最悪の悪循環に陥るのです。
リーダーとしての役割は監督になること
リーダーとしてのあなたの役割は、もはや一人のプレイヤーとして最高のパフォーマンスを出すことではありません。
部下一人ひとりの力を引き出し、チームとして1以上の成果を生み出す「監督」になることです。あなた一人の力は1かもしれませんが、6人の部下の力を引き出せば、チームの力は6にも7にもなり得ます。
「自分がやった方が早い」という思考は、プレイヤーとしての優秀さの証です。しかし、リーダーとなった今、その思考は卒業すべき過去の成功体験です。
指導の自信のなさが自己肯定感の低下とストレスに繋がる
部下をうまく指導できない状況が続くと、「自分はリーダー失格なんじゃないか」と、どんどん自信を失っていきますよね。
プレイヤー時代には感じなかった無力感や、自分の能力への疑念が生まれ、強いストレスを感じてしまうのは、あなただけではありません。

指導への自信のなさは、さらなる悪循環を生み出します。部下とのコミュニケーションが億劫になり、必要なフィードバックを避けたり、逆に不安から過度なマイクロマネジメントに走ってしまったりします。
部下は「信頼されていない」と感じ、あなたは「部下が期待通りに動いてくれない」と、お互いに不満が募るばかりです。
上司からは「もっと厳しくやれ」と叱責され、部下からは反発される。そんな板挟みの状態で、誰にも悩みを相談できずに一人で抱え込んでしまうリーダーは少なくありません。こうしたストレスが積み重なると、心身の健康を損なうことにもなりかねません。
今までとは全く別のスキル
しかし、この自信のなさは、あなたの能力が低いからではありません。
これまで求められてきた「個人の成果を出す能力」と、今求められている「チームで成果を出す能力」は、全く別のスキルです。誰もが最初は戸惑い、失敗を繰り返しながら、新しいスキルを身につけていくのです。
自己肯定感が下がっている状態では、新しい挑戦をしたり、自分を客観的に見つめ直したりする気力も湧きにくいものです。
まずは、「自分は今、新しい役割を学んでいる最中なのだ」と、自分自身を認めてあげてください。リーダー失格などと、自分を責める必要は全くありません。
指導に自信が持てないのは、適切な方法論を知らないだけです。水泳の方法を知らない人が、いきなり上手く泳げないのと同じです。
注意できない上司やリーダーが明日から使える!部下を導く伝え方と育成術
- 関係を壊さない「直接注意しない上司」の伝え方3選
- I(アイ)メッセージを活用したフィードバック術
- 定期的な1on1ミーティングで心理的安全を確保する方法
- ミスを成長機会に変える具体的なフィードバックフレーズ集
- リーダーとして持つべきマインドセットへの転換
関係を壊さない「直接注意しない上司」の伝え方3選
部下との関係を壊さずに問題を改善に導くには、直接的な物言いを避ける工夫が有効です。「直接注意しない上司」と聞くと、責任を放棄しているように思えるかもしれませんが、これは相手への配慮に基づいた高度なコミュニケーションスキルなのです。
ここでは、明日から使える3つの伝え方を紹介します。

第三者を主語にして伝える方法
これは、「私」でも「あなた」でもなく、第三者を主語にして客観的な事実や影響を伝えるテクニックです。
「君の報告書、誤字が多いよ」と直接指摘する代わりに、「この報告書をクライアントが見たら、会社の信頼に関わるかもしれないね」と伝えます。
部下は個人的に攻撃されたと感じにくく、自分の行動が周囲に与える影響を客観的に考えるきっかけになります。これにより、部下の心理的な抵抗が小さくなり、指摘を受け入れやすくなります。
質問によって本人に気づかせる方法
上から一方的に指示するのではなく、質問を投げかけることで、部下自身に問題点や改善策を考えさせるアプローチです。
例えば、締切を守れない部下に対して、「どうしていつも遅れるんだ」と詰問するのではなく、「このタスクを時間内に終えるには、どんな進め方が良さそうかな?」と問いかけます。自分で考え、答えを出すプロセスを通じて、部下は当事者意識を持ち、行動変容に繋がりやすくなります。一緒に原因を探り、解決策を検討する姿勢が大切です。
自分の失敗談を話す方法
「自分は過去こうやって成功した」という成功体験を語るのではなく、あえて自分の失敗談を共有する方法です。
「俺も若い頃、同じようなミスをして大変だったんだ」と話すことで、上司も完璧な人間ではないと分かり、部下は心理的な壁を感じにくくなります。
失敗談を通じて、「だから、こうならないように気をつけてほしい」というメッセージを伝えることで、アドバイスが説教臭くならず、素直に相手の心に届きます。
I(アイ)メッセージを活用したフィードバック術
部下にフィードバックを伝える際、最もやってはいけないのが主語を「あなた(You)」にして話すことです。
「あなたはなぜ報告しないのか」「あなたのやり方は間違っている」といったYouメッセージは、相手を非難し、追い詰める響きがあります。これでは、部下は防御的になり、反発心を抱くだけです。

そこで活用したいのが、主語を「私(I)」に置き換える「I(アイ)メッセージ」です。
これは、相手の行動に対して、自分がどう感じたか、どう影響を受けたかを主観的な事実として伝えるコミュニケーション手法です。
客観的な事実(相手の行動)と、自分の主観(気持ちや影響)をセットで伝えるのがポイントです。
具体的な伝え方は、「(事実)+(気持ち・影響)」の構造で組み立てます。例えば、部下が相談なく仕事を進めてしまった場合、以下のようになります。
Iメッセージ:「(事実)相談なしで進んでいると、(気持ち)状況が分からなくて私は心配になんだ」
締め切りを守れなかった部下に対しては、以下のような形で話します。
Iメッセージ:「(事実)締め切りに間に合わないと、(影響)チーム全体のスケジュールに影響が出て、私は困ってしまうんだ」
Iメッセージで伝えることで、あなたの主観的な感情や考えがストレートに伝わります。
非難ではなく、あくまで「私はこう感じている」という表現なので、部下は事実を事実として受け止めやすくなります。自分の行動が上司にどんな影響を与えているかを具体的に知ることで、行動を改めようという内発的な動機付けにつながるのです。
記述的なフィードバックも意識
フィードバックの際には、相手の行動をできるだけ明確に、見たまま客観的に伝える「記述的なフィードバック」を意識することも重要です。
例えば、「会議で居眠りをするなんてありえない」というのは主観的な評価ですが、「会議中、10分ほど目を閉じていましたね」というのは記述的なフィードバックです。
この客観的な事実に、Iメッセージを組み合わせることで、より効果的な伝え方が可能になります。
定期的な1on1ミーティングで心理的安全を確保する方法
部下が安心して本音を話せる環境作りに、1on1ミーティングは非常に効果的です。
1on1とは、上司と部下が1対1で定期的に行う対話の機会を指します。この時間の主役はあくまで部下であり、あなたが評価や指示をする場ではありません。
部下が安心して何でも話せる「心理的安全性」を確保することが、1on1の最も重要な目的です。

心理的安全性が高い職場では、部下は「こんなことを言ったら評価が下がるかも」と心配することなく、自分の意見や悩みを率直に話せます。
これにより、問題の早期発見や、部下のエンゲージメント向上に繋がり、結果としてチーム全体のパフォーマンスが向上します。
では、どうすれば心理的安全性の高い1on1が実現できるのでしょうか。ポイントはいくつかあります。
心理的安全性の高い1on1とは
まずは、週に1回30分など、定期的に開催することをルールにしましょう。そして、会議室などプライバシーが確保できる場所で行うことが大切です。
ミーティングの冒頭では、「今週どうだった?」「何か困っていることはない?」といったオープンな質問から始め、部下が話し出すのを待ちます。
上司は聞き役に徹し、部下の話を遮ったり、一方的にアドバイスしたりするのはNGです。部下の言葉に深く耳を傾け、「そうなんだね」「なるほど」と肯定的に相槌を打つことで、部下は「受け入れてもらえている」と感じ、安心して話せるようになります。
もし部下が何も話してくれなくても、焦る必要はありません。沈黙も大切なコミュニケーションの一部です。
あなたが根気強く対話を続けることで、徐々に信頼関係が築かれ、部下も少しずつ心を開いてくれるようになります。
1on1は、部下との信頼関係を築き、チームの土台を強くするための大切な時間です。
ミスを成長機会に変える具体的なフィードバックフレーズ集
部下のミスを指摘するとき、伝え方一つで相手の受け取り方は大きく変わります。ミスをただの失敗で終わらせるのではなく、次につながる貴重な成長機会に変える。
そのために有効なのが、具体的なフィードバックです。ここでは、明日から使える具体的なフレーズをいくつか紹介します。

フィードバックの基本は、褒める言葉で改善点を挟む「サンドイッチ型」です。いきなり問題点を指摘するのではなく、まずはポジティブな点から伝えることで、相手は話を受け入れる態勢ができます。
報告・連絡・相談が遅い部下へ
「〇〇さん、いつもクライアントへの丁寧な対応、本当にありがとう。すごく助かっているよ。一つ相談なんだけど、もし可能なら、プロジェクトの進捗をもう少し早い段階で共有してくれると、僕も早めにサポートに入れるから嬉しいな。これからも丁寧な仕事、期待しているね。」
このように、感謝と期待を伝えつつ、具体的な改善行動をお願いする形です。
同じミスを繰り返す部下へ
「この資料、分かりやすくまとめてくれてありがとう。ただ、一点だけ気になったんだけど、前回と同じ計算ミスがあったみたいなんだ。何かやり方で困っている部分があるかな?もしよかったら、一緒にチェック方法を見直してみないか?」
相手を責めるのではなく、原因を一緒に探る姿勢を見せることで、部下も素直に相談しやすくなります。
目標を達成できていない部下へ
「いつもチームのために頑張ってくれて、本当に感謝しているよ。ただ、残念ながら今月も目標には届かなかったようだね。目標達成のために、僕に何か手伝えることはないかな。一度、今のアプローチ方法について一緒に話してみようか。」
努力を認めた上で、解決策を共に考えるパートナーとしてのスタンスを示します。
リーダーとして持つべきマインドセットへの転換
「部下に嫌われたくない」という気持ちから注意をためらうのは、一見優しさのように見えます。しかし、それは本当に部下のためになっているのでしょうか。
厳しいことを言わずに部下の成長機会を奪うのは、ある意味で「無関心」であり、リーダーとしての責任を放棄しているとも言えるかもしれません。

真のリーダーシップとは、短期的に嫌われることを恐れず、部下の長期的な成長を願って本気で向き合う姿勢です。
これを「Tough Love(タフ・ラブ)」、つまり「厳しさの中にある愛情」と呼びます。
注意や指導は、部下の人格を否定するためのものではありません。それは、「もっと成長してほしい」「より良い仕事をしてほしい」という、あなたの愛情表現なのです。
このマインドセットに転換するためには、まず物事の見方を変えることから始めましょう。例えば、「部下のミス」を「指導のチャンス」と捉え直すのです。ミスを指摘することは、部下にとって自分の課題に気づく絶好の機会になります。
常に学び変化し続ける姿勢を見せることも重要
また、リーダーであるあなた自身が、常に学び、変化し続ける姿勢を見せることも重要です。あなたが率先して新しい仕事に取り組んだり、勉強会に参加したりする姿は、部下にとって何よりの刺激になります。
リーダーが完璧である必要はありません。むしろ、自分の弱さや失敗をオープンに語れるリーダーの方が、部下は親近感を覚え、信頼を寄せるものです。
「注意は愛情である」というマインドセットは、すぐには身につかないかもしれません。しかし、日々のコミュニケーションの中で、「これは部下の成長のためなんだ」と意識し続けることで、あなたの言葉や行動は必ず変わってきます。
その変化はチーム全体に良い影響を与え、部下もあなたの厳しさの奥にある愛情を理解してくれる日が来るでしょう。
まとめ
部下に注意できない悩みは、多くのリーダーが抱える共通の課題です。その背景には、パワハラへの恐怖や関係悪化への懸念、そして自分自身の指導への自信のなさが隠れています。
しかし、必要な注意を怠ることは、部下の成長機会を奪い、チーム全体の生産性を低下させることにも繋がります。
大切なのは、性格を変えようとするのではなく、伝え方の「スキル」を身につけることです。
「あえて注意しない」ことで信頼関係を築き、Iメッセージや具体的なフィードバックで、相手を尊重しながらこちらの意図を正確に伝えます。
定期的な1on1を通じて心理的安全性を確保し、ミスを成長の糧に変える関わり方を続けることが重要です。
そして何より、「注意は愛情である」というマインドセットを持つこと。部下の未来を心から願うあなたの真摯な姿勢は、必ず相手に伝わります。
この記事で紹介したステップを参考に、明日から一つでも実践してみてください。あなたのリーダーとしての新しい一歩が、チームをより良い方向へと導くはずです。
最後に今回の記事をまとめます。
- 人に注意できないのは性格の問題ではなく、伝え方のスキル不足が原因である
- 部下への注意は攻撃ではなく、成長を促すためのフィードバックと捉える
- パワハラを恐れる自己防衛の心理が、注意をためらわせる一因である
- 感情的な人格否定であるパワハラと、事実に基づく正当な指導は明確に違う
- 誰も注意しない職場は、真面目な社員の意欲を削ぎ、チームの生産性を下げる
- Z世代の部下には、感情論ではなく論理的で納得できる説明が響く
- 「自分がやった方が早い」という思考は、部下の成長機会を奪う罠である
- リーダーの役割はプレイヤーではなく、チーム全体の力を引き出す監督である
- 指導への自信のなさは、求められるスキルがプレイヤー時代と変化したことが原因である
- 第三者を主語にしたり、質問を投げかけたりして、直接的な表現を避ける
- 主語を「私」にするIメッセージで、非難ではなく自分の気持ちや影響を伝える
- 定期的な1on1ミーティングで部下の話を聞き、心理的安全性を確保する
- フィードバックは、褒める言葉で改善点を挟む「サンドイッチ型」が有効である
- 指摘する際は人格ではなく「行動」に焦点を当て、未来志向で対話する
- 「注意は愛情」というマインドセットを持ち、部下の長期的な成長を願う