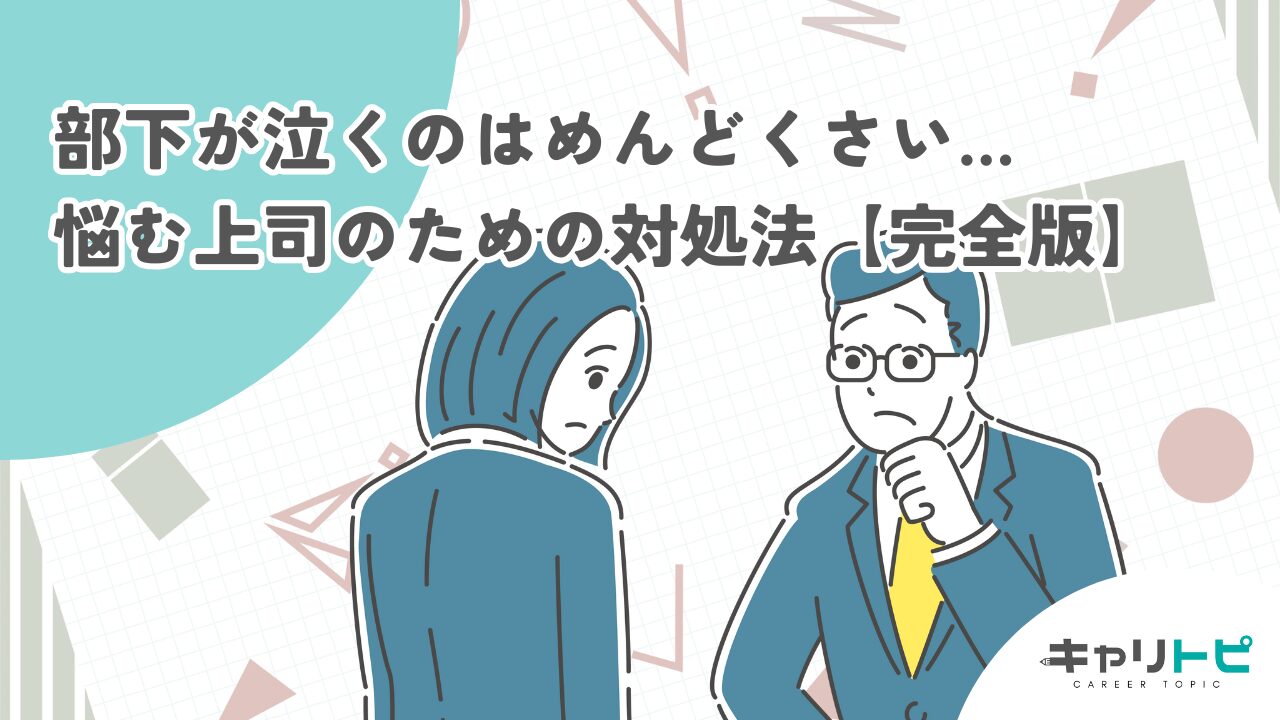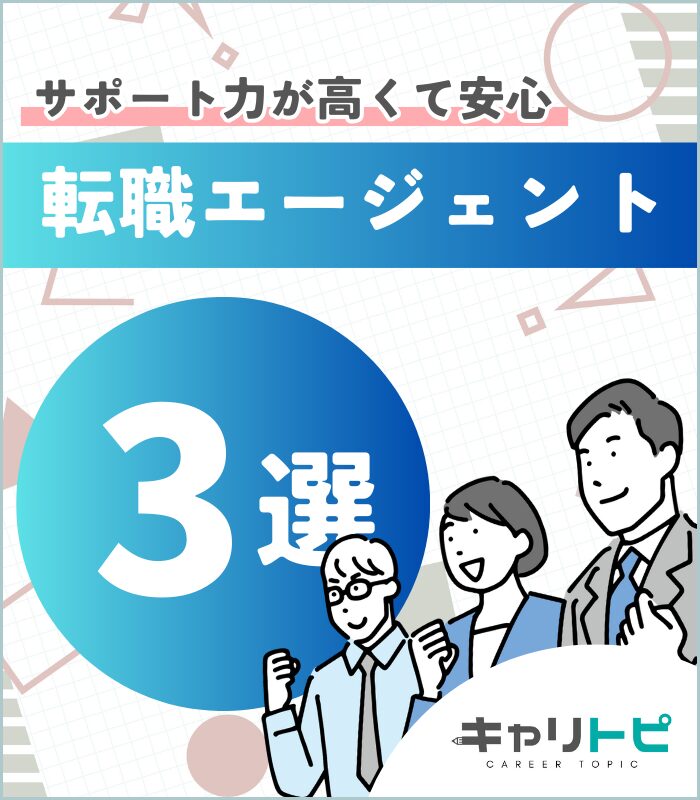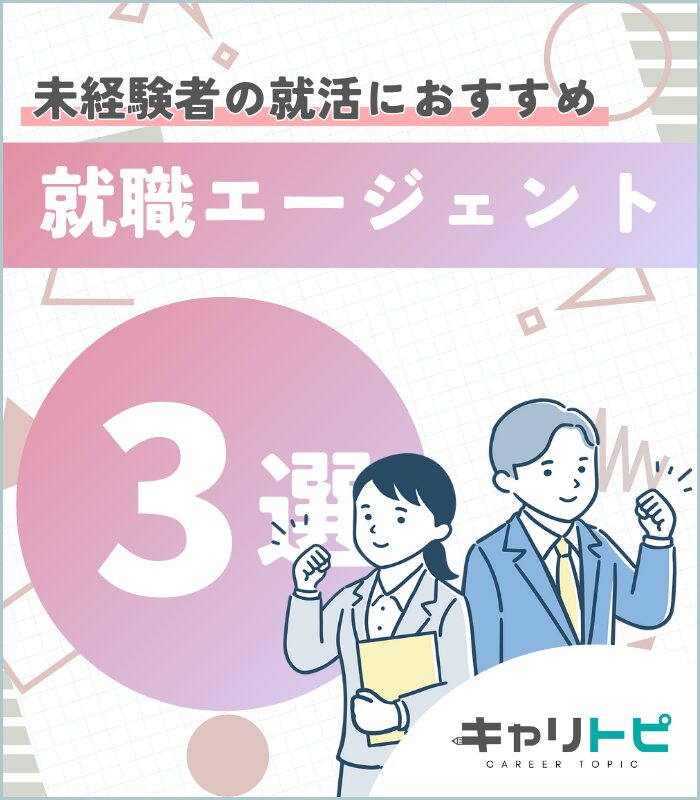部下を注意したら泣かれてしまった…

また泣くと思うと指導するのがめんどくさい…
このような状況に、頭を悩ませている管理職の方は少なくないかもしれません。
部下の成長を願って指導しているつもりでも、涙を見せられると「自分の言い方が悪かったのでは?」と自信をなくしたり、業務が滞ってしまいます。
もしかしたら、「すぐ泣く部下をうざいと感じてしまう自分はダメな上司なのか?」と一人で抱え込んでしまうかもしれません。
そこでこの記事では、部下が泣くのはめんどくさいと悩む方に向けて、泣く部下の心理や具体的な対処法をまとめました。
泣く部下への対応を誤ると、パワハラになってしまったり、周りに管理不足と見られるリスクも潜んでいます。
正しい解決策を知って、部下との関係改善を目指していきましょう。
- 部下が泣いてしまう心理的な背景
- やってはいけないNG行動と具体的な対処法
- 指導とパワハラの境界線
- 部下との信頼関係を再構築するためのヒント
部下が泣くのはめんどくさい理由と心理的な背景
- まずは知りたい女性部下が泣く心理
- なぜ部下は泣くのか?男性の心理
- すぐ泣く部下はうざいという態度はNG
- 部下が泣いたらパワハラ?指導との境界線
- 注意すると泣く部下への正しい指摘の仕方
まずは知りたい女性部下が泣く心理
女性部下が職場で泣いてしまう背景には、様々な心理が隠されています。一括りにはできませんが、主に考えられる理由を理解することが、適切な対応への第一歩です。

一つは、自分自身への不甲斐なさです。特に真面目で責任感の強い部下は、ミスを指摘された際に自分の力不足を痛感し、悔しさや情けなさから涙を流すことがあります。
これは、上司を困らせようとしているのではなく、自分自身を責めている結果であることが多いのです。
次に、女性特有の生理現象が影響している可能性も考慮に入れる必要があります。
PMS(月経前症候群)などの影響でホルモンバランスが乱れ、感情が不安定になり、普段なら受け流せる言葉にも過敏に反応してしまうことがあります。
また、中には被害者意識から泣いてしまうケースも見られます。
自分の意に沿わないことがあると、涙を見せることで周囲の同情を買い、状況を有利に進めようとする心理が働く場合です。
しかし、多くの場合は意図的ではなく、承認欲求や自己主張が満たされないもどかしさが、涙として表れていると考えられます。
承認欲求との関連
女性は、仕事において昇進や地位向上そのものよりも、「誰かの役に立っている」「組織に貢献できている」という実感に価値を見出す傾向があります。
そのため、成長を促すための厳しい指導が、本人にとっては「自分は認められていない」「大切にされていない」というメッセージとして受け取られ、涙に繋がってしまうことがあるのです。
なぜ部下は泣くのか?男性の場合の心理
「泣くのは女性」というイメージが強いかもしれませんが、男性部下が職場で涙を見せることもあります。
その背景にある心理は、女性の場合と共通する部分も多いですが、特有のプレッシャーが関係していることも考えられます。

男性が人前で泣くことへの社会的な抵抗感は根強く、それを乗り越えて涙が溢れるとき、それは相当なプレッシャーやストレスを抱えているサインかもしれません。
例えば、過大な業務量や達成困難な目標に対する重圧、自身の能力への絶望感などが挙げられます。
また、プライドが傷ついたときの強い悔しさや怒りが、涙として現れることもあります。
理不尽な評価を受けたり、努力を正当に認めてもらえなかったりした際に、言葉にできない感情が涙に変わるのです。
上司としては、男性が泣くという事態を重く受け止め、「よほどのことがあったのだろう」という視点で、その背景にある問題に真摯に耳を傾ける姿勢が求められます。
すぐ泣く部下はうざいという態度はNG
指導のたびに部下に泣かれると、思わず「うざい」「またか…」と感じてしまう気持ちは、人間として自然な反応かもしれません。
しかし、その感情を態度や言葉に出してしまうのは絶対に避けるべきです。

その態度は信頼関係を破壊する
「泣いても解決しない」「すぐに泣くな」といった言葉で突き放したり、あからさまに面倒な表情を見せたりする行為は、部下の心をさらに深く傷つけます。
部下は「この人には何も相談できない」と感じ、心を閉ざしてしまいます。結果として、報告・連絡・相談が滞り、さらに大きな業務上のミスにつながる危険性すらあるのです。
上司のその態度は、百害あって一利なしと心得ましょう。
部下も、好きで泣いているわけではないケースがほとんどです。感情のコントロールが追い付かない自分自身に、もどかしさを感じています。
「うざい」という感情を一旦脇に置き、まずは冷静に「なぜこの部下は泣いているのだろう?」とその背景に意識を向けることが、解決への第一歩となります。
部下が泣いたらパワハラ?指導との境界線
「部下を泣かせてしまったら、それはパワハラになるのでは?」と不安になる上司は多いでしょう。
しかし、「部下が泣いた」という事実だけで、即座にパワハラと認定されるわけではありません。
重要なのは、その言動が「業務上必要かつ相当な範囲を超えているか」どうかです。

厚生労働省が定義するパワーハラスメントの3つの要素は以下の通りです。
- 職場において優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
この3つを全て満たす場合に、パワハラと判断される可能性があります。
つまり、業務上の正当な理由に基づく指導であれば、たとえ結果的に部下が泣いてしまったとしても、それ自体が問題なのではありません。
指導とパワハラの具体例
以下の表で、正当な指導とパワハラになり得る言動の違いを確認しましょう。
| 項目 | OK:業務上、適正な指導 | NG:パワハラになり得る言動 |
|---|---|---|
| 叱責の場所 | 他の従業員がいない会議室など、人目を避けた場所を選ぶ | 他の従業員がいる前で、大声で叱責する |
| 叱責の内容 | 具体的なミスや改善すべき行動について、客観的な事実を伝える | 「だからお前はダメなんだ」など、人格や能力を否定する言葉を使う |
| 叱責の時間 | 要点をまとめて、端的に伝える | 何時間も延々と、同じ内容を繰り返し説教する |
| 目的 | 部下の成長を促し、業務を改善することが目的である | 相手を精神的に追い詰めることが目的になっている |
部下の涙は、あなたの指導方法を見直すきっかけにはなりますが、必要以上に萎縮する必要はありません。
あくまで客観的な事実に基づき、相手の成長を願う姿勢で接することが大切です。
注意すると泣く部下への正しい指摘の仕方
では、具体的にどのように注意すれば、部下を無用に傷つけず、内容を正しく伝えられるのでしょうか。いくつかのポイントをご紹介します。

指導方法を少し変えるだけで、部下の受け取り方は大きく変わります。感情的な対立を避け、建設的なコミュニケーションを目指しましょう。
人前での注意は絶対に避ける
これは基本中の基本です。他のメンバーがいる前での指摘は、部下の自尊心を著しく傷つけます。
「晒し者にされた」という気持ちから、指導の内容が全く頭に入ってこないばかりか、強い反発心を生む原因となります。
必ず、1対1になれる会議室などに場所を移してから話しましょう。
まずは事実確認から入る
いきなり「なぜこんなミスをしたんだ!」と問い詰めるのではなく、「この件について、どういう状況だったか教えてもらえる?」と、まずは部下からの説明を求めます。
これにより、部下は「自分の話を聞いてもらえる」と感じ、少し冷静さを取り戻すことができます。また、上司が知らない事情があったことが判明する場合もあります。
「I(アイ)メッセージ」で伝える
「You(ユー)メッセージ」(「あなたはなぜ~しないんだ」)は、相手を責めるニュアンスが強くなります。
そうではなく、「I(アイ)メッセージ」(「私は~してくれると助かる」「私は~だと感じた」)を使いましょう。
例えば、「なぜ報告が遅いんだ!」ではなく、「報告が遅れると、私も次の対応が遅れてしまって困るんだ」と伝えることで、相手への攻撃ではなく、自分の状況を伝える形になり、受け入れられやすくなります。
行動と人格を切り離す
指摘するのは、あくまで「今回のミス」という具体的な「行動」についてです。
「いつもそうだよね」「君は本当に〇〇だ」といった、相手の「人格」を否定するような言い方は絶対にやめましょう。
今回の事実に限定して、具体的にどう改善してほしいのかを伝えることが重要です。
部下は泣くものなのか?めんどくさいを乗り越える対処法
- すぐ泣くのはHSPの特性?専門家の見解
- もしかして部下が泣くのは鬱のサイン?
- 部下が泣いてかわいいから抱きしめるのは厳禁
- 泣かせた後が肝心!具体的なフォロー方法
- もう「部下が泣いてめんどくさい」で悩まない
すぐ泣くのはHSPの特性?専門家の見解
「少し注意しただけなのに、なぜこんなに傷つくのだろう?」と感じる場合、その部下はHSP(Highly Sensitive Person)の気質を持っている可能性があります。

HSPとは、生まれつき感受性が強く、外部からの刺激に非常に敏感な人々のことを指します。病気ではなく、あくまで個人の特性です。
HSPの人は、他人の感情や場の空気を察知する能力が高い一方で、些細な言葉に深く傷ついたり、人一倍疲れやすかったりする傾向があります。
HSPの部下への接し方のヒントは以下の通りです。
抽象的な表現を避ける
「いい感じでやっといて」のような曖昧な指示は不安にさせます。「この手順で、〇時までにここまでお願いします」と具体的に伝えましょう。
一度に多くの情報を与えない
情報を処理するのに時間がかかるため、指示は一つずつ出すのが効果的です。
ポジティブなフィードバックを増やす
できたことを具体的に褒めることで、安心感を与え、自己肯定感を育むことができます。
HSPかどうかは判断できない
HSPかどうかを上司が判断することはできませんし、決めつけるべきでもありません。
ただ、「人より刺激に敏感なタイプなのかもしれない」という視点を持つことで、部下の行動への理解が深まり、より適切なコミュニケーション方法が見つかるかもしれません。
もしかして部下が泣くのは鬱のサイン?
頻繁に泣く、あるいは以前と比べて明らかに涙もろくなったという変化が見られる場合、それはメンタル不調、特にうつ病のサインである可能性も視野に入れる必要があります。

涙もろくなること以外にも、以下のような変化がないか注意深く観察してみてください。
- 明らかに元気がない、表情が暗い日が続いている
- 好きだったことへの興味を失っているように見える
- 集中力が低下し、以前はしなかったようなミスが増えた
- 遅刻や早退、欠勤が増えた
- 食欲が極端にない、あるいはありすぎる
- 「眠れない」「疲労感がとれない」と漏らしている
これらのサインが複数当てはまり、2週間以上続いているような場合は、注意が必要です。
上司として部下の健康を気遣うことは大切ですが、うつ病の診断は医師にしかできません。「うつ病じゃないの?」と直接的に指摘することは、部下を追い詰める可能性があるため絶対に避けてください。
もし心配な場合は、「最近、辛そうだね。もしよかったら話を聞くよ」「会社の相談窓口や、産業医に相談してみるのも一つの手だよ」と、専門家への相談を促す形でサポートするのが適切です。
部下の心理的負担になっている問題を聞き出し、業務量の調整や部署異動の検討など、上司としてできる範囲で環境改善に協力する姿勢を見せることが大切です。
部下が泣いてかわいいから抱きしめるのは厳禁
泣いている部下を見て、庇護欲から「かわいい」と感じてしまうことがあるかもしれません。しかし、その感情を行動に移すのは絶対にNGです。
特に、身体的な接触は、いかなる理由があってもセクシャルハラスメントと見なされる可能性が極めて高いです。
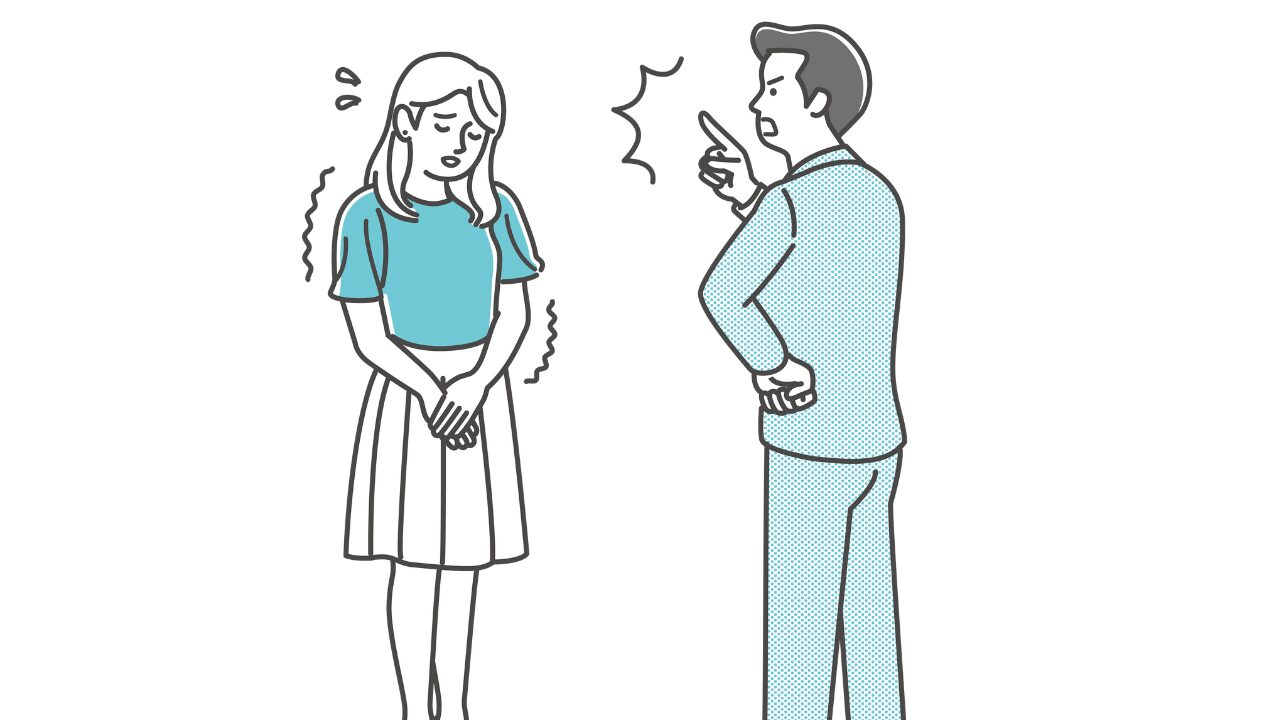
善意で肩を叩いたり、頭を撫でたりしたつもりが、相手にとっては「不快な身体的接触」と受け取られるリスクがあります。
ましてや「抱きしめる」といった行為は、相手との信頼関係を完全に破壊し、深刻な問題に発展しかねません。
距離感を保つことが最大の誠意
部下が泣いているときは、励ましの気持ちから身体的な接触に頼るのではなく、言葉と姿勢で寄り添うことが重要です。
ティッシュを差し出す、飲み物を勧める、落ち着くまで静かに待つなど、適切な物理的・心理的距離を保つことが、上司としての誠意ある対応です。
泣いてしまった後が肝心!具体的なフォロー方法
指導中に部下が泣いてしまった場合、その場をどう収めるかも重要ですが、それ以上にその後のフォローが部下との信頼関係を左右します。

「気まずいから…」と放置するのが最悪の選択です。雨降って地固まる、というように、この機会を関係改善のチャンスと捉えましょう。
まず、部下が泣き出してしまったら、一旦話を中断しましょう。「少し休憩しようか」「落ち着くまで待つから大丈夫だよ」と声をかけ、相手が感情を整理する時間を与えます。
可能であれば、トイレや休憩室など、その場から離れて一人になれる時間を作るのも有効です。
そして、部下が落ち着いたら、あるいは日を改めて、必ずフォローアップの面談を設定してください。その際のポイントは以下の通りです。
上司の意図を改めて伝える
「あの時、厳しい言い方になってしまったかもしれないけど、君の成長を期待してのことだったんだ」というように、指導の背景にあったポジティブな意図を伝えます。
部下の気持ちを聞く
「あの時、どんな気持ちだった?」「何が一番つらかった?」と、相手の感情や考えを丁寧にヒアリングします。ここで重要なのは、否定せずに最後まで聞き切ることです。
今後の対策を一緒に考える
「今回のミスを防ぐために、次からどうすればいいか一緒に考えよう」と、未来志向の対話に繋げます。
上司が一方的に解決策を示すのではなく、部下自身に考えさせることで、主体性を引き出します。
まとめ:部下が泣くのはめんどくさい…悩む上司のための対処法【完全版】
いかがでしたか?部下が泣くとめんどくさいと感じるのは、多くの管理職が抱える正直な気持ちです。
しかし、その背景には部下自身の悔しさや不安、時には心身の不調など、様々な要因が隠されていることがお分かりいただけたかと思います。
この記事でご紹介した対処法やフォローを実践することで、部下との関係は必ず改善できます。一人で悩まず、明日からのコミュニケーションにぜひ活かしてみてください。
最後に今回の記事をまとめます。

- 部下が泣くのはあなたを困らせるためではない
- 悔しさや不安、プレッシャーなど様々な心理が背景にある
- 女性は自分への不甲斐なさや承認欲求から泣くことがある
- 男性の涙は相当なストレスのサインかもしれない
- 「うざい」という態度は信頼関係を壊すだけ
- 泣いた事実だけでパワハラにはならない
- 業務上必要かつ相当な範囲の指導は正当な行為
- 指導する際は1対1の環境を確保する
- 人格ではなく具体的な行動を指摘する
- HSPなど生まれ持った気質が関係している可能性も考慮する
- 頻繁に泣くなど変化が見られたらメンタル不調のサインかも
- うつ病の診断は医師にしかできず、安易な指摘は禁物
- 身体的接触はセクハラになるため絶対に避ける
- 泣かれた後は必ずフォロー面談を設定する
- 上司の真意を伝え、部下の気持ちを聞き、対策を共に考える