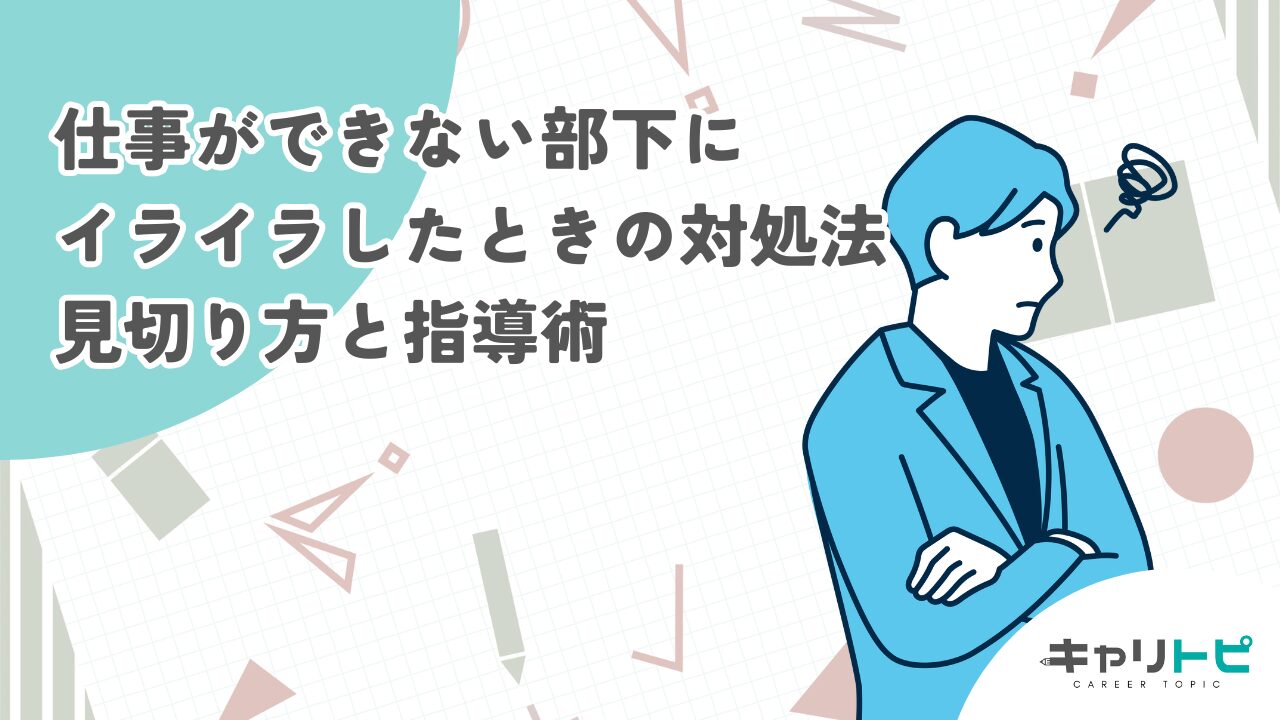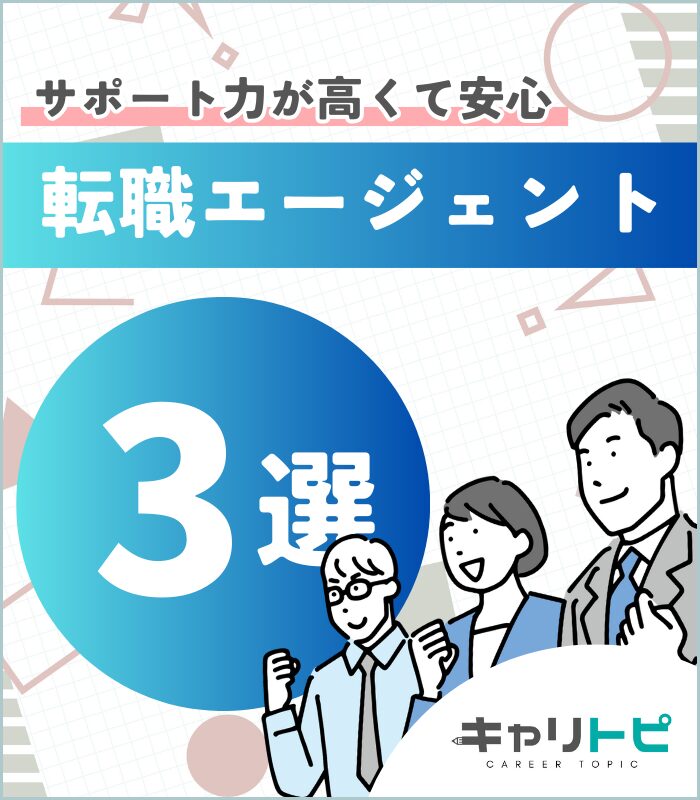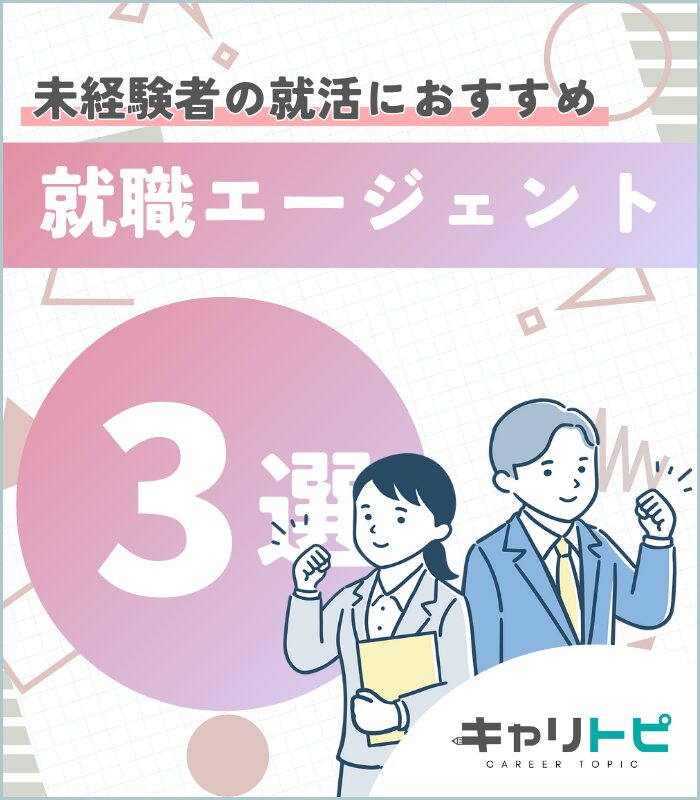仕事ができない部下に対し、ついイライラしてしまうことはないでしょうか?
指導しても改善が見られない場合、「どうするべきなのか」と悩むはずです。これは、多くの管理職が抱える共通の課題です。
この記事では、仕事ができない部下にイライラしてしまうときの対処法を詳しくまとめました。
仕事ができない部下を放置することは、チーム全体の生産性低下にも繋がり、部下に対するストレスをひとりで抱え込むのは、非常に辛いものです。
部下との向き合い方や見切りをつけるべき期間の目安、具体的な対処法を一緒にチェックしていきましょう。
- 仕事ができない部下の特徴と原因
- ストレスと放置のリスク
- イライラを解消する対処法と指導のコツ
- 部下を見切る期間の目安や注意点
仕事ができない部下に対するイライラの原因と特徴
- まず知るべき仕事ができない部下の特徴
- 無意識にやってない?部下を潰す上司の特徴
- ストレスと仕事ができない部下との関係
- 仕事ができない部下を放置するリスク
- まず仕事ができない部下をどうするべきなのか?
まず知るべき仕事ができない部下の特徴
部下に対して「仕事ができない」と感じる背景には、いくつかの共通した特徴が存在します。これらの特徴を客観的に把握することが、問題解決の第一歩です。
具体的にどのような行動が、上司のイライラやチームの課題に繋がっているのでしょうか。

主な特徴として、以下の点が挙げられます。
| 特徴 | 具体的な行動例 |
|---|---|
| 指示待ちで自主性がない | 言われたことしかやらず、自分で考えて行動しようとしない。常に指示を待っており、次の作業を自ら見つけられない。 |
| 同じミスを繰り返す | 以前に指導した内容を忘れ、何度も同じ間違いをする。ミスの原因を分析せず、根本的な改善が見られない。 |
| 報告・連絡・相談が不十分 | 業務の進捗状況や発生した問題を適切なタイミングで報告しない。自己判断で仕事を進め、後からトラブルが発覚するケースが多い。 |
| 責任感や当事者意識が低い | 仕事のミスを他人のせいにしたり、言い訳をしたりする。与えられた仕事に対する責任感が欠けており、品質や納期への意識が低い。 |
| コミュニケーション能力の課題 | 会話のキャッチボールが成立しなかったり、相手の意図を汲み取れなかったりする。質問や相談をためらい、一人で問題を抱え込むことがある。 |
これらの特徴は、一つだけでなく複数当てはまることが多いです。
あなたの部下がどのタイプに当てはまるかを見極めることで、より効果的なアプローチを考えるヒントになります。
無意識にやってない?部下を潰す上司の特徴
部下の成長が見られない原因は、部下本人だけにあるとは限りません。実は、上司の言動が部下のパフォーマンスを低下させ、成長を妨げている可能性も考えられます。
知らず知らずのうちに、部下を潰す上司になっていないか、自身の行動を振り返ってみましょう。
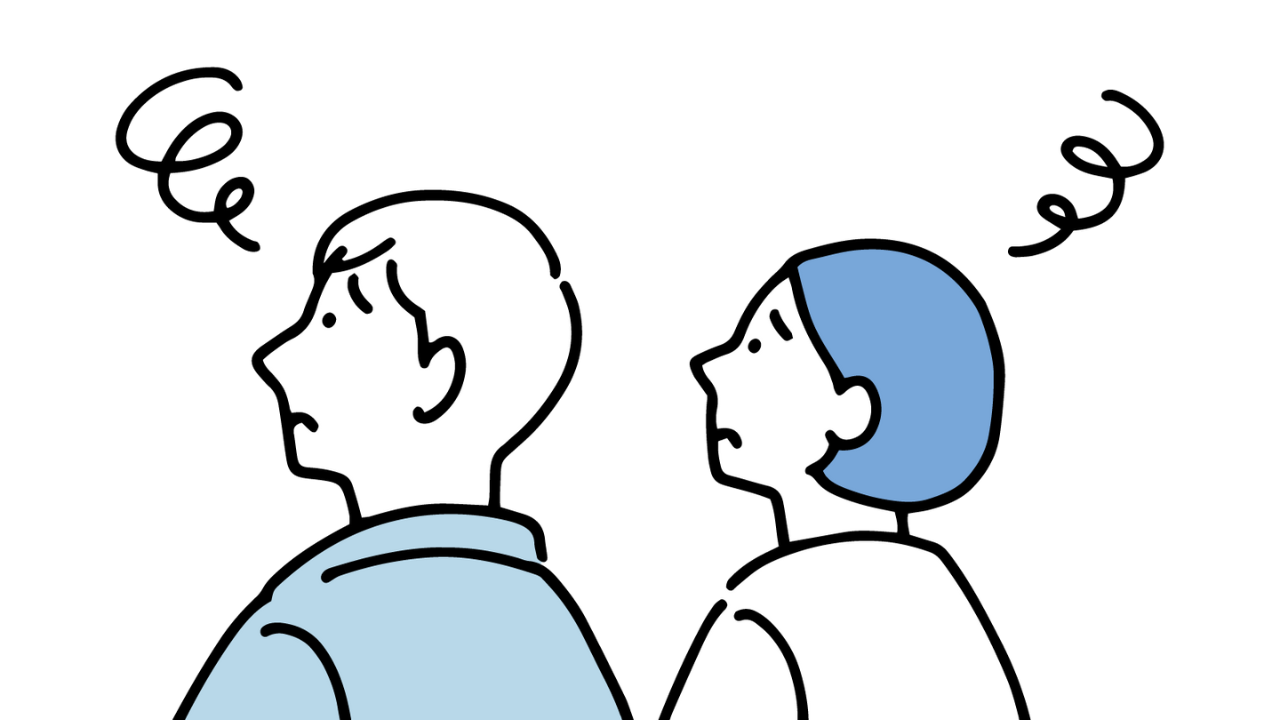
注意すべき上司の行動として、以下のような特徴に心当たりはありませんか。
一つでも当てはまる場合、あなたのマネジメントスタイルが部下の成長を阻害しているかもしれません。
完璧主義で細かいミスを許さない
部下の失敗に対して過度に厳しく叱責し、挑戦する意欲を削いでしまう。
指示が曖昧・抽象的
具体的な指示を出さず、「よしなにお願い」といった丸投げをしてしまう。部下は何をすればよいか分からず、行動に移せません。
自分でやった方が早いと仕事を奪う
部下の成長を待てず、結局自分が業務を巻き取ってしまう。これは部下の学習機会を奪う行為です。
感情的に叱責する
論理的な指導ではなく、イライラした感情をそのままぶつけてしまう。部下は萎縮し、相談しにくい雰囲気になります。
マイクロマネジメント
部下の業務を細かく監視し、過剰に干渉する。部下の自主性を尊重せず、信頼していないというメッセージになります。
ストレスと仕事ができない部下との関係
仕事ができない部下への対応は、上司に大きな精神的負担をかけます。
部下のミスをフォローしたり、遅れたスケジュールを調整したりすることで、自身の業務時間が圧迫されるだけでなく、精神的な疲弊にも繋がります。

部下が原因で感じるストレスには、以下のようなものがあります。
- 期待通りに動いてくれないことへの失望感
- 同じことを何度も教える徒労感
- チームの目標が達成できないことへの焦り
- 自分の指導力不足を責める自己嫌悪
このようなストレスが蓄積すると、上司自身のパフォーマンス低下やモチベーションの喪失に繋がりかねません。
さらに、イライラした態度が他のチームメンバーにも伝染し、職場全体の雰囲気を悪化させる原因にもなります。
仕事ができない部下を放置するリスク
「もう何を言っても無駄だ」と、仕事ができない部下を放置してしまうのは、最も避けるべき対応の一つです。
放置は一見、短期的なストレスから解放されるように感じるかもしれませんが、長期的にはさらに深刻な問題を引き起こす可能性があります。

部下への関与を諦めることで、以下のようなリスクが発生します。
チーム全体の生産性低下
放置された部下の業務は、質の低いまま遂行されるか、停滞します。その結果、他のメンバーがカバーする必要が生じ、チーム全体の業務効率が著しく低下します。
他の部下の不満とモチベーション低下
特定の部下だけが許されている状況は、真面目に働く他のメンバーの不公平感に繋がります。「なぜあの人だけ」という不満が広がり、チームの士気は大きく下がるでしょう。
重大なコンプライアンス違反や事故の発生
適切な管理が行われないことで、部下が大きなミスや情報漏洩などの問題を引き起こすリスクが高まります。これは企業の信頼を揺るがす事態に発展しかねません。
上司自身の評価低下
部下の育成や管理は上司の重要な責務です。部下の問題を放置することは、マネジメント能力の欠如と見なされ、あなた自身の評価を下げることになります。
まず仕事ができない部下をどうするべきなのか?
部下に対して「仕事ができない」というレッテルを貼る前に、上司として試すべき具体的なアプローチがあります。
感情的になるのではなく、冷静に状況を分析し、段階的に対策を講じることが重要です。
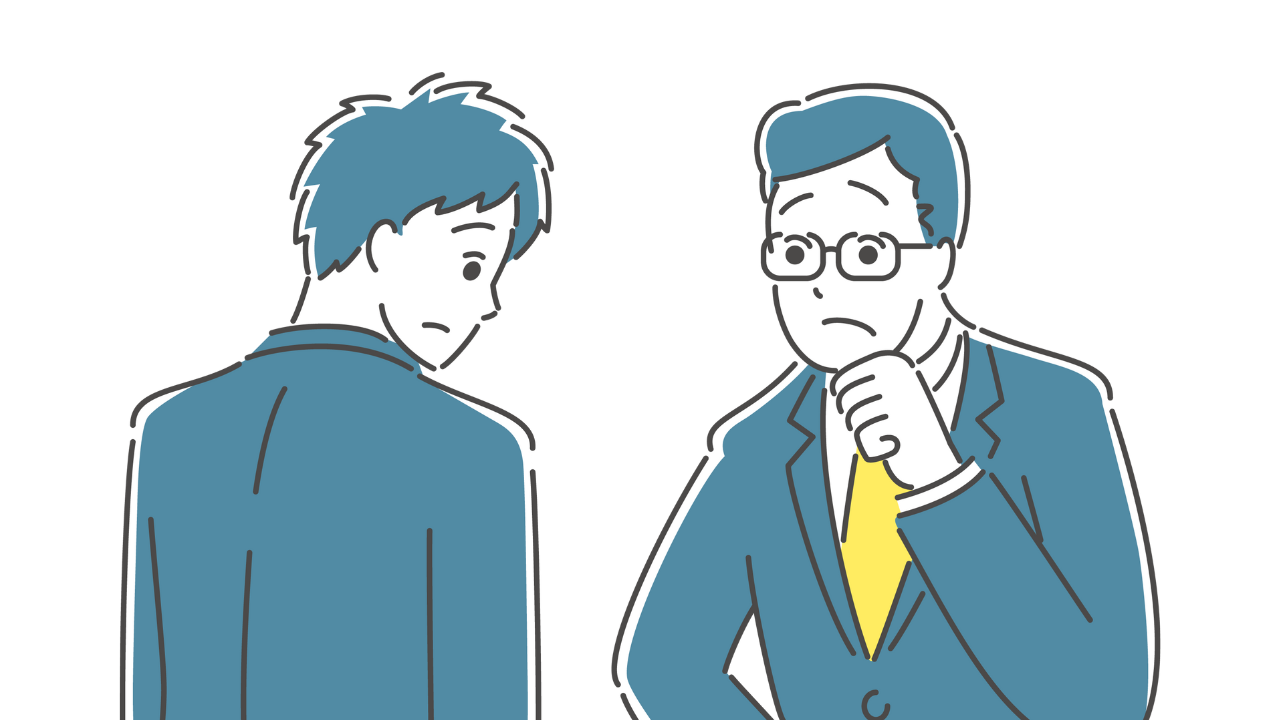
まずは以下の3つのステップから始めてみましょう。
簡単な仕事から成功体験を積ませる
仕事ができないと感じる部下は、成功体験が不足し、自信を失っている場合があります。
まずは「これなら絶対にできる」というレベルの簡単な仕事を任せ、達成感を感じさせましょう。
小さな成功を積み重ねることで、仕事への前向きな姿勢を引き出すことができます。
仕事ができない原因を本人に考えさせる
上司が一方的に原因を決めつけるのではなく、部下自身に「なぜうまくいかないのか」を考えてもらう機会を設けます。
「どうすれば改善できると思う?」と問いかけ、内省を促すことが大切です。上司はあくまでサポート役として、本人の気づきを引き出すことに徹しましょう。
相談しやすい雰囲気を作る
部下が「分からないことを聞けない」「ミスを報告しづらい」と感じている可能性もあります。
普段から挨拶を交わしたり、1on1ミーティングなどで定期的に対話の時間を持つなど、心理的安全性を高める工夫が必要です。
部下が安心して相談できる関係を築くことが、問題の早期発見に繋がります。
仕事ができない部下へのイライラを解消するためのアクション
- 今日からできる部下にイライラしない方法
- 見切りをつける期間の目安
- 発達障害や病気の可能性も
- 見逃さないで!部下が辞めそうな兆候は?
今日からできる部下にイライラしない方法
部下へのイライラは、自身の感情をコントロールすることで、ある程度軽減することが可能です。感情に振り回されるのではなく、冷静に対処するための具体的な方法をいくつか紹介します。

イライラした時こそ、一歩引いて客観的に状況を見る意識が大切です。すぐに実践できる方法を取り入れてみましょう。
自分の感情を整理する
「イライラする」という感情を、「なぜ」「何に」イライラしているのか具体的に分解してみましょう。
例えば、「納期を守らないから」ではなく、「納期遅延によって顧客からの信頼を失うことを恐れているから」のように、感情の根源にある自分の価値観や懸念を突き止めると、冷静さを取り戻しやすくなります。
部下の立場になって考えてみる
なぜ部下がそのように行動するのか、一度相手の立場に立って考えてみることも有効です。もしかしたら、業務の指示が分かりにくかったり、本人が別の困難を抱えていたりするのかもしれません。
相手の視点を持つことで、一方的な決めつけを防ぎ、理解しようとする姿勢が生まれます。
期待値のハードルを下げる
「自分ならこれくらいできるはず」という高い基準を部下に当てはめていませんか。
部下の現状のスキルや経験を正しく認識し、期待値のハードルを現実的なレベルまで下げることが大切です。
最初から100点を求めるのではなく、60点でもできたら褒める、というようにスモールステップで成長を見守る姿勢が、自身の心の余裕に繋がります。
見切りをつける期間の目安
部下の育成には時間と忍耐が必要ですが、いつまでも改善が見られない場合、どこかのタイミングで「見切りをつける」という判断も必要になります。

ただし、この判断は慎重に行うべきです。一般的に、指導期間の目安を設けて、その達成度合いで判断することが推奨されます。
指導期間と判断の目安
以下は、あくまで一般的な目安です。業種や職種、部下の経験年数によって期間は調整してください。
| 指導期間 | 目標レベル | 見切り判断のポイント |
|---|---|---|
| 1〜3ヶ月 | 基本的な業務を覚え、指示されたことを正確にこなせる | この段階で指示理解や基本的な業務遂行に大きな課題がある場合、適性そのものに問題がある可能性を考慮し始めます。 |
| 3〜6ヶ月 | ある程度、自主的に業務を進められるようになる | 半年経っても改善の兆しが全く見られない、同じミスを繰り返す、成長意欲が感じられない場合は、見切りを本格的に検討する段階です[6]。 |
| 6ヶ月以上 | 安定して成果を出し、チームに貢献できる | この期間を過ぎても育成コストがかかり続ける場合は、配置転換や、場合によっては退職勧奨なども視野に入れた次のステップを人事部と相談する必要があります。 |
重要なのは、この期間内に「上司としてやるべき指導を全てやりきったか」を自問することです。
発達障害や病気の可能性も
何度指導しても改善が見られない場合、「もしかして発達障害や何かの病気が関係しているのでは?」と考えることがあるかもしれません。
実際に、注意欠陥・多動性障害(ADHD)や自閉スペクトラム症(ASD)などの発達障害の特性が、仕事上の困難に繋がっているケースも存在します。

注意:上司が診断することは絶対にできません
「仕事ができない=発達障害」と安易に結びつけるのは非常に危険です。単なるスキル不足や、やる気の問題である可能性も十分にあります。
上司が部下に対して「発達障害ではないか」と指摘したり、診断したりすることは絶対に許されません。これは重大な人権侵害にあたる可能性があります。
もし、以下のような特性が複数見られ、本人が著しく困っている様子であれば、専門家への相談を促すというアプローチが考えられます。
- 極端にミスや抜け漏れが多い
- 指示の受け取り方にズレが生じやすい
- 複数の業務を同時に進めることが著しく苦手
- 場の空気を読む・暗黙のルールの理解が難しい
対応に苦慮する場合は、決して一人で抱え込まず、人事部や産業医に相談してください。
企業によっては、発達障害のある社員への合理的配慮に関する窓口が設けられていることもあります。
まずは会社の制度を確認し、専門家の助言を仰ぐことが、本人にとっても組織にとっても最善の策です。
発達障害に関する情報については、公的機関や専門機関のウェブサイトを参照することをお勧めします。
例えば、厚生労働省や発達障害情報・支援センターのサイトには信頼できる情報が掲載されています。(参照:厚生労働省 みんなのメンタルヘルス)
見逃さないで!部下が辞めそうな兆候は?
指導がうまくいかず、部下との関係が悪化すると、部下が退職を考え始めることがあります。突然の退職はチームにとって大きな痛手となるため、その兆候を早期に察知し、対策を講じることが重要です。

以下に挙げるのは、部下が退職を考えているときに見られる可能性のあるサインです。
コミュニケーションの変化
- 口数が減り、雑談やプライベートな話を避けるようになる
- 会議での発言が消極的になる、あるいは逆に批判的な態度が増える
- 上司とのコミュニケーションを避けるようになる
勤務態度の変化
- 遅刻や早退、急な欠勤が増える
- これまで熱心に取り組んでいた業務への意欲が明らかに低下する
- 会社の飲み会やイベントへの参加を断るようになる
将来に関する言動
- 将来のキャリアプランについて話さなくなる
- 社外のセミナーや勉強会に頻繁に参加し始める
- 身だしなみが変化したり、業務時間内に私用の電話が増えたりする
これらの兆候は、あくまで可能性の一つであり、必ずしも退職に直結するわけではありません。しかし、複数のサインが見られる場合は、1on1ミーティングなどで率直に話を聞く機会を設けるなど、早めの対応が求められます。
まとめ:仕事ができない部下にイライラしたときの対処法|見切り方と指導術
いかがでしたか?仕事ができない部下にイライラしてしまうのは、多くの管理職が抱える共通の悩みです。
重要なのは、感情的に対応するのではなく、部下の特徴や自身の指導法を客観的に分析し、具体的な行動に移すことです。
本記事で紹介した対処法が、仕事ができない部下のイライラを解消し、より良いチーム作りへの一歩になれば嬉しいです。
最後に今回の記事をまとめます。

- 仕事ができない部下の特徴には指示待ちや同じミスの繰り返しなどがある
- 上司自身の曖昧な指示や完璧主義が部下の成長を妨げている可能性もある
- 部下への対応は上司の精神的ストレスに直結しパフォーマンスを低下させる
- 部下を放置することはチーム全体の生産性低下や士気の悪化に繋がる
- まずは簡単な仕事で成功体験を積ませることから始める
- なぜうまくいかないか本人に考えさせ内省を促す
- 相談しやすい心理的安全性の高い環境を整える
- 自身の感情を分解しイライラの根源を理解する
- 相手の立場に立って考えることで一方的な決めつけを防ぐ
- 部下への期待値を現実的なレベルに調整し心の余裕を持つ
- 3ヶ月から6ヶ月の期間を目安に指導計画を立てる
- 期間内に改善が見られなければ見切りや配置転換を検討する
- 安易に発達障害と結びつけず専門家への相談を促す
- 部下の退職の兆候を早期に察知し対話の機会を持つ
- 一人で抱え込まず人事部や他の管理職に相談する