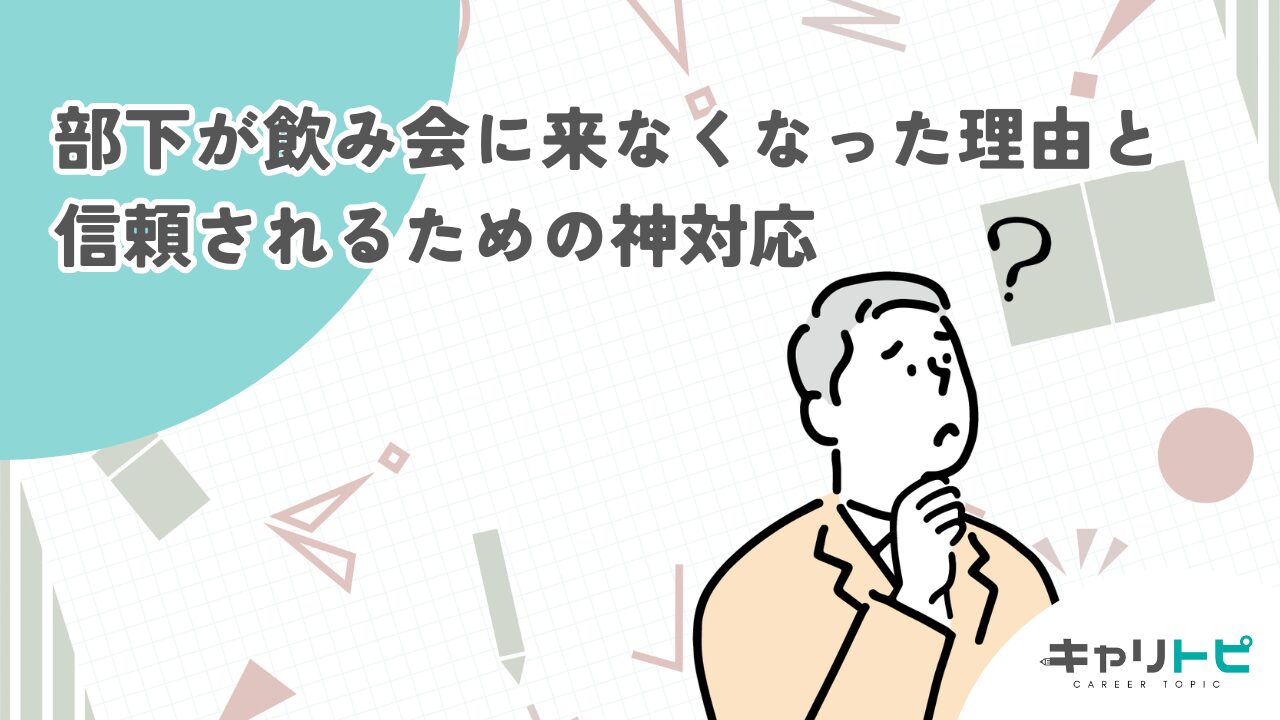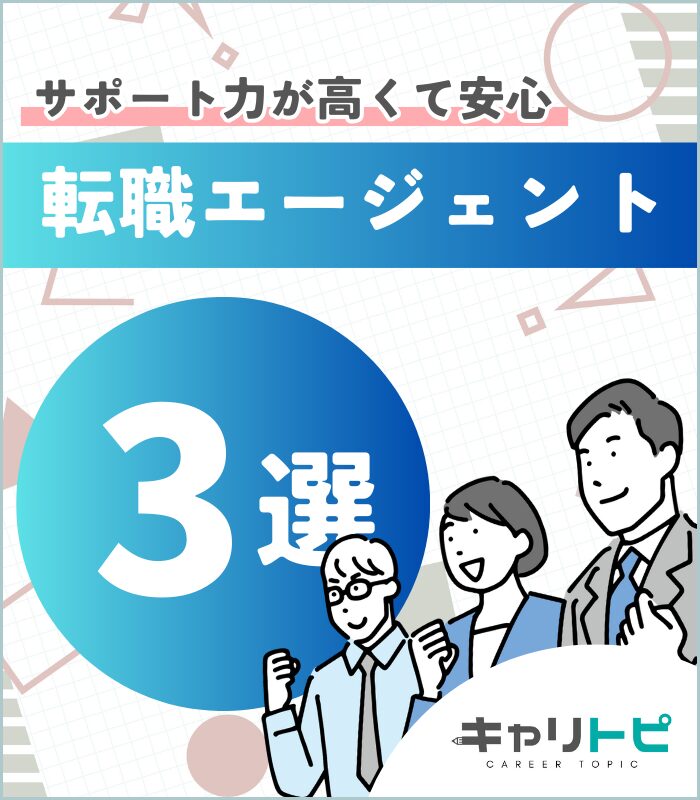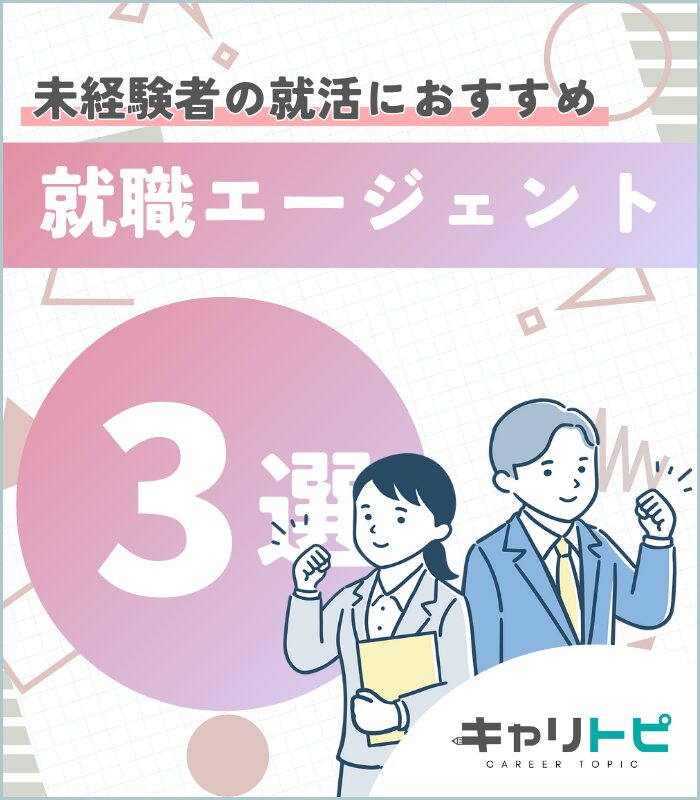「最近、部下が飲み会に来なくなった」と悩んでいませんか?
チームの一体感を大切にしたい上司にとって、大きな悩みかもしれません。しかし、部下が飲み会に参加しない背景には、その人なりの理由があります。
飲み会に来ない人の心理を理解しないまま、参加を促してしまうと、飲み会の強制参加がパワハラと見なされるリスクも潜んでいます。
この記事では、部下が飲み会に来なくなった背景を深く掘り下げ、飲み会に行かないことが賢いとされる現代の価値観、上司としてどう対応すべきかまで、詳しく解説します。
- 部下が飲み会に来なくなった理由と心理
- 飲み会に行かないことが賢いと言われる背景
- パワハラを避け部下と良好な関係を築く方法
- 飲み会に代わる新しいコミュニケーションの形
なぜ部下は飲み会に来なくなったのか?理由と心理を深堀り
- 飲み会来ない人の特徴とその理由
- 飲み会に来ない人の心理
- 職場の飲み会には一切行かない人の割合
- 飲み会に行かないのは賢いという考え方
- 飲み会に行かない成功者とは
- 飲み会に行かないと嫌われるという不安も
飲み会来ない人の特徴と理由
部下が飲み会に参加しなくなった背景には、個人の価値観やライフスタイルの変化が大きく影響しています。
以前のように「会社の付き合いは当然」という考え方は、もはや通用しなくなりつつあります。

主な理由として、プライベートな時間を重視する傾向が強まっていることが挙げられます。
特にZ世代と呼ばれる若手社員の約9割がワークライフバランスを重視しているという調査結果もあり、仕事終わりの貴重な時間を、残業代の出ない飲み会に費やしたくないと考えるのは自然なことです。
他にも、以下のような理由が考えられます。
気遣いによる疲弊
上司や先輩にお酒を注いだり、料理を取り分けたり、会話が途切れないように話題を提供したりと、飲み会の場では常に気を遣う必要があります。
リラックスできるはずの場で、かえって疲れてしまうことを避けたいと感じる人は少なくありません。
経済的な負担
参加費が自己負担である場合、経済的な理由から参加をためらうケースもあります。特に若手社員にとっては、数千円の出費でも大きな負担になり得ます。
体質的な問題
アルコールが体質的に受け付けない、または健康上の理由で飲酒を控えている人もいます。このような個人的な事情を、わざわざ説明することに抵抗を感じる場合もあるでしょう。
楽しくない・メリットを感じない
そもそもお酒の席や大人数での集まりが苦手な人もいます。また、上司の自慢話や説教が延々と続くような飲み会では、参加するメリットを見いだせないと感じるのも無理はありません。
飲み会に来ない人の心理
飲み会に来ないという行動の裏には、さまざまな心理が隠されています。
上司としては、部下がどのような気持ちで断っているのかを想像することが、すれ違いを防ぐ第一歩となります。

一つは、「自分の時間をコントロールしたい」という自己決定への欲求です。
仕事は与えられた業務をこなすものですが、勤務時間外の過ごし方くらいは自分で決めたい、という気持ちは誰にでもあるものです。飲み会への参加が、プライベートへの過度な干渉だと感じられることがあります。
また、「嫌われたくないが、行きたくない」という葛藤を抱えているケースも少なくありません。
上司や同僚との関係を悪化させたくないという思いと、飲み会に参加することへの抵抗感との間で、心理的なストレスを感じている可能性があります。
断る際に、「申し訳ない」という気持ちを抱えながらも、自分の意思を優先しているのです。
「それは業務ですか?」の裏にある心理
部下から「その飲み会は業務ですか?」と問われた経験がある方もいるかもしれません。
この言葉は、単なる反発ではなく、業務とプライベートの境界線を明確にしたいという意思表示です。自分の時間を守るための、いわば防衛的な反応と捉えることができます。
さらに、「そもそも飲み会でのコミュニケーションは不要」と考えている場合もあります。
業務に必要な連携は、あくまで就業時間内に行うべきであり、アルコールの力を借りた「飲みニケーション」に頼る必要性を感じていないのです。
部下は、上司が思う以上に職場の人間関係に気を配っています。
彼らが飲み会に来ないのは、あなた個人を嫌っているからではなく、飲み会という形式そのものが、彼らの価値観やライフスタイルに合わないことがほとんどなのです。
職場の飲み会には一切行かない人の割合
ある調査では「飲みニケーションは不要」と考える人が64.5%にものぼるという結果が出ています。(引用元:飲みニケーションはありなしか、社会人831人に聞いてみました)
これは、3人に2人は仕事上のコミュニケーションを深めるために、必ずしも飲み会が必要だとは考えていないことを示唆しています。

また、なかには「職場の飲み会に一切行かない」と決めている人もいて、その傾向は年々強まっていると言われています。
この背景には、前述の通り、若者世代を中心にワークライフバランスを重視する価値観が浸透していることが大きく関わっています。
プライベートな時間を自己投資や趣味、家族との時間に使いたいと考える人が増えているのです。
飲み会不参加は退職のサイン?
注意すべき点として、これまで頻繁に参加していた部下が急に来なくなった場合、それは転職活動などを始めたサインである可能性もあります。
自分の自由な時間を、次のキャリアに向けた準備に充てているケースがあるため、コミュニケーションの変化には気を配る必要があるでしょう。
飲み会に行かないのは賢いという考え方
現代において、職場の飲み会に参加しないという選択は、単なる消極的な行動ではなく、「賢い」選択であるという考え方が広がっています。
これは、時間という有限な資源を、自分にとって最も価値のあるものに投資するという、戦略的な視点に基づいています。

飲み会に行かないことで得られるメリットは、主に以下の3点が挙げられます。
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 時間の有効活用 | 飲み会に参加すれば2〜3時間は拘束されます。この時間を、スキルアップのための学習、副業、趣味、家族との対話など、自己成長やQOL(生活の質)向上に直結する活動に充てることができます[12][6]。 |
| 経済的・身体的負担の軽減 | 参加費用の節約はもちろん、飲酒による翌日の体調不良(二日酔いなど)を避けられます。これにより、常に万全の状態で仕事に取り組むことができ、生産性の維持にも繋がります[6]。 |
| 不要なストレスからの解放 | 人間関係の気遣いや、興味のない話を聞き続けるといった精神的なストレスから解放されます[4]。精神的な平穏を保つことは、長期的なキャリアを考える上で非常に重要です。 |
もちろん、飲み会には偶発的な情報交換や、普段話さない人との交流といったメリットも存在します。
しかし、これらのメリットは、失われる時間やコストに見合わないと判断する人が増えているのです。
飲み会に行かない成功者とは
「成功者は飲み会に行かない」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
これは、彼らが単に人付き合いが嫌いなのではなく、自分の時間を極めて戦略的に使っていることの表れです。

飲み会に行かない成功者には、以下のような共通した特徴が見られます。
明確な目標を持っている
彼らは自分のキャリアや人生において、何を達成したいかが明確です。そのため、その目標達成に直接つながらない活動には、時間を割かない傾向があります。
自己投資を怠らない
飲み会を断って確保した時間を、読書や資格の勉強、専門スキルの習得といった自己投資に充てています。この積み重ねが、他者との差を生み出す源泉となります。
時間の価値を理解している
成功者は「時は金なり」を実践しています。彼らにとって、数時間の飲み会は、時に数万円、数十万円の機会損失に相当すると考えるのです。
人脈を厳選している
誰とでも広く浅く付き合うのではなく、自分の成長に資する質の高い人脈を大切にします。飲み会よりも、1対1のランチや、目的のはっきりした勉強会などを好む傾向があります。
すべての飲み会を否定しているわけではない
重要なのは、彼らは「全ての飲み会」を否定しているわけではないということです。
自分の目標達成に繋がる、有益な情報交換ができる、あるいは尊敬する人物が参加するなど、明確な目的とメリットがある会には、むしろ積極的に参加します。
彼らは、飲み会に参加するか否かを、常に投資対効果で判断しているのです。
飲み会に行かないと嫌われるという不安も
部下の立場からすれば、「飲み会に行かないと、上司や同僚に嫌われるのではないか」「協調性がないと思われ、評価が下がるのではないか」という不安も感じています。

実際に、上司の世代や企業の文化によっては、飲み会への参加率がチームの一体感の指標と見なされたり、「付き合いが悪い」というネガティブな印象を持たれたりする可能性はゼロではありません。
上司から「俺の顔が潰れる」といったプレッシャーをかけられたという話も聞かれます。
しかし、時代は確実に変化しています。近年では、飲み会への参加有無よりも、実際の業務における成果や能力で個人を評価する企業が増えています。
個人の価値観の多様性を尊重し、プライベートな時間に干渉しないことが、現代的なマネジメントの主流となりつつあります。
コミュニケーション不足への配慮は必要
ただし、飲み会に行かない選択をする場合でも、業務に支障が出ないよう、他の形でのコミュニケーションを意識することは重要です。
例えば、ランチに誘う、業務中の雑談を大切にするなど、飲み会以外の方法で良好な関係を築く努力を怠らないことが、不必要な誤解を避ける鍵となります。
部下が飲み会に来なくなったら上司がすべきこと
- 部下をダメにする上司の特徴
- 飲み会に部下を強制参加させるのはパワハラ?
- 飲み会に代わるコミュニケーションの形
- 新しい関係構築のヒント
- 部下が飲み会に来なくなった時代のまとめ
部下をダメにする上司の特徴
部下が飲み会に来なくなったとき、その原因が自分にある可能性を省みることは、非常に重要です。

知らず知らずのうちに、「部下をダメにする上司」になっていないか、以下の特徴を確認してみましょう。
| 項目 | 部下をダメにする上司の特徴 | 部下に信頼される上司の振る舞い |
|---|---|---|
| 飲み会での言動 | 自分の武勇伝や説教ばかり話す[3]。部下のプライベートに踏み込みすぎる。 | 部下の話に耳を傾け、聞き役に徹する。ポジティブな話題を提供する。 |
| 価値観の押し付け | 「飲み会は絶対参加」という自分の価値観を疑わず、不参加の部下を「付き合いが悪い」と決めつける[2]。 | 多様な価値観を認め、参加・不参加は個人の自由であると明言する。 |
| 時間の意識 | 一次会で終わらず、二次会、三次会へと無理に連れ回そうとする[3]。 | 開始時間と終了時間を明確にし、長時間の拘束は避ける。 |
| 公平性 | 飲み会に参加する部下だけを可愛がり、業務評価に影響させるような言動をとる[13]。 | 飲み会への参加有無で部下を差別せず、評価は業務成果で公平に行う。 |
特に、自分の成功体験をベースにした「飲みニケーション」の価値観を部下に押し付けてしまうことは、最も避けなければならない行為の一つです。
時代や世代が違えば、コミュニケーションのあり方や価値観も変わるという事実を受け入れる必要があります。
もし一つでも当てはまる点があれば、今日から行動を変えてみませんか。上司が変われば、部下の反応も少しずつ変わっていくはずです。
飲み会に部下を強制参加させるのはパワハラ?
結論から言うと、業務時間外の飲み会への参加を強制する行為は、パワーハラスメント(パワハラ)に該当する可能性が非常に高いです。
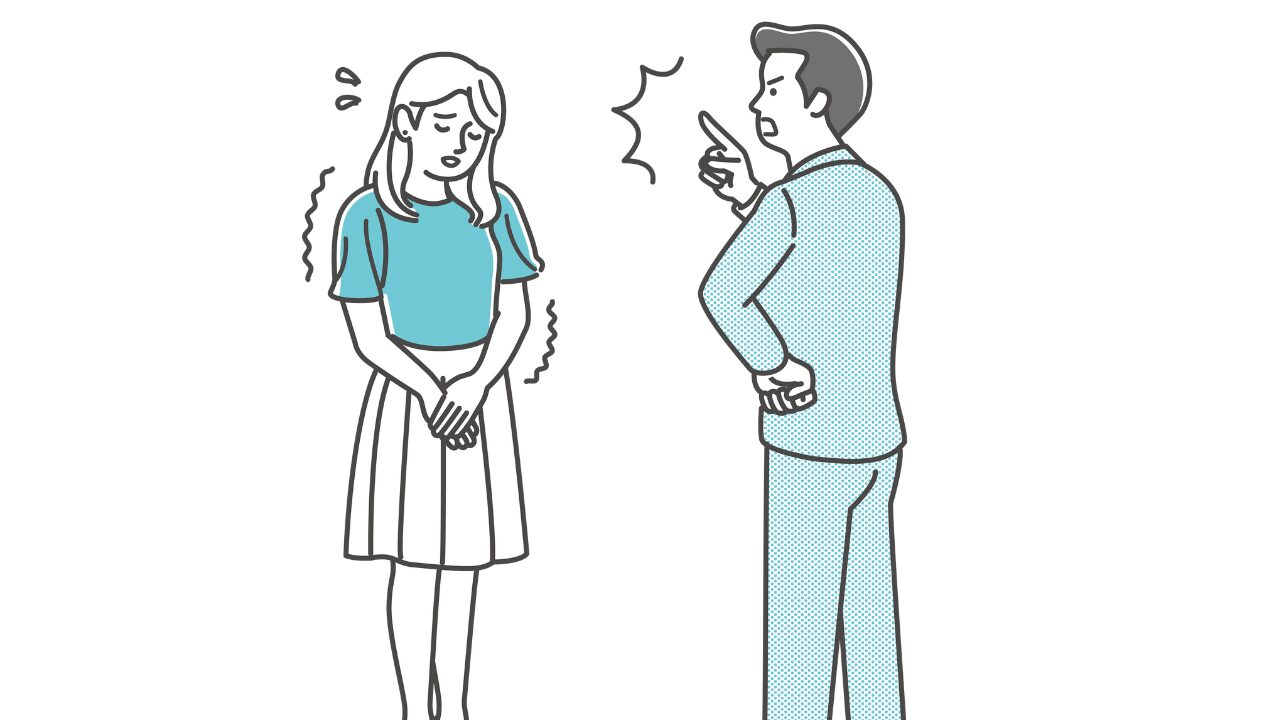
パワハラは、労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)で定義されており、以下の3つの要素をすべて満たすものとされています。
- 職場における優越的な関係を背景とした言動であること
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
- 労働者の就業環境が害されること
飲み会の強制は、まさにこれらの要素に当てはまりやすい典型的な例です。
パワハラとみなされる可能性のある言動
以下のような言動は、部下に精神的苦痛を与え、就業環境を害するものとしてパワハラと認定されるリスクがあります。
- 「全員参加が当たり前だ」と不参加を許さない雰囲気を作る
- 断った部下に対して「ノリが悪い」「付き合いが悪い」などと非難する
- 不参加を理由に、その後の業務で不利益な扱い(無視、過度な叱責など)をする
- 「これは業務命令だ」と言って参加を強要する(業務であれば賃金の支払い義務が発生します)
実際に、部下から「しつこい誘いがストレスだ」と人事部に通報されたり、訴訟に発展したりするケースも存在します。
飲み会に代わるコミュニケーションの形
部下が飲み会に来なくなったからといって、コミュニケーションを諦める必要は全くありません。むしろ、これを機に、時代に合った新しいコミュニケーションの形を模索するチャンスと捉えましょう。
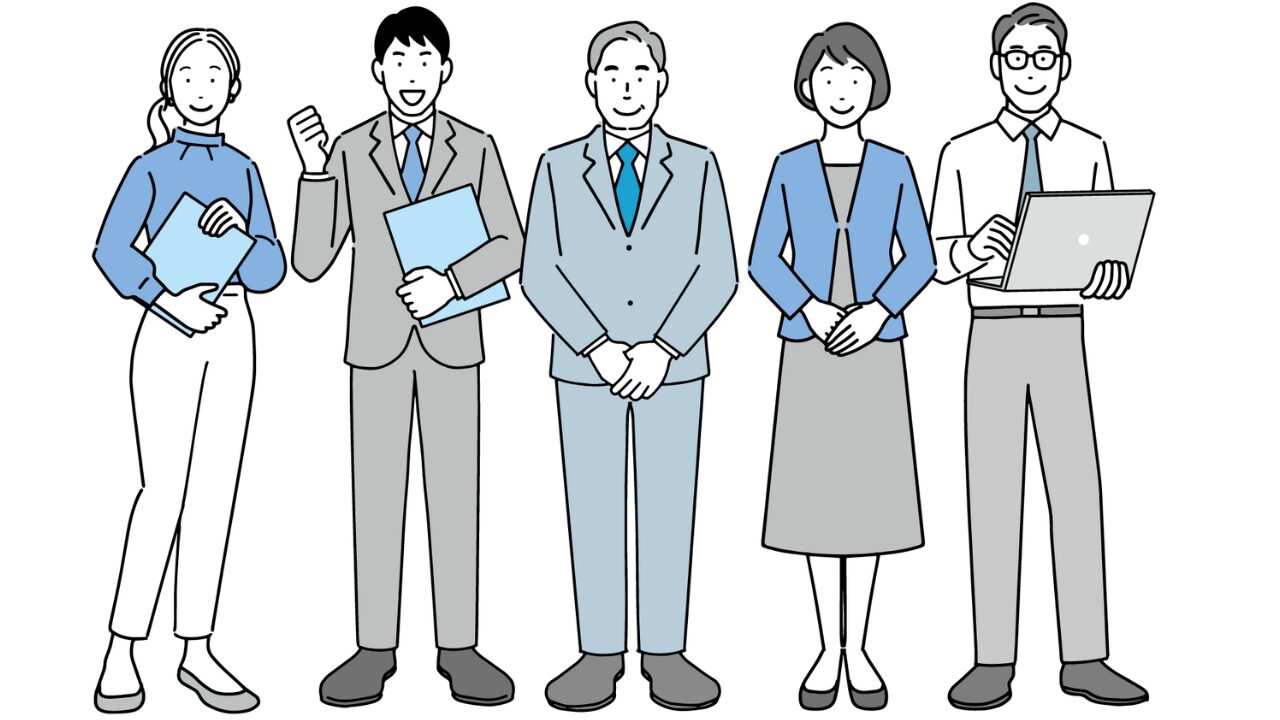
飲み会に代わる有効な手段として、以下のようなものが挙げられます。
ランチミーティング
就業時間内に行うランチは、最も手軽で効果的な代替案です。
アルコールが入らないため、業務に関連した真面目な話から、プライベートな軽い雑談まで、建設的なコミュニケーションが期待できます。費用は会社経費で負担するのが望ましいでしょう。
1on1ミーティングの充実
定期的な1on1ミーティングの時間を、単なる業務報告の場ではなく、部下のキャリア観や悩みに耳を傾ける対話の時間として活用します。
信頼関係が深まれば、自然とコミュニケーションは円滑になります。
社内イベントの工夫
飲み会以外の社内イベントを企画するのも良い方法です。
例えば、ボードゲーム大会、スポーツ活動、社内勉強会など、アルコールを介さない共通の体験は、チームの一体感を醸成するのに役立ちます。
オンラインでのコミュニケーションも活用
チャットツールでの雑談チャンネルの作成や、短時間のオンライン朝会なども有効です。テキストベースのコミュニケーションは、対面が苦手な部下にとっても参加のハードルが低いというメリットがあります。
重要なのは、コミュニケーションの選択肢を複数用意し、部下が自分に合った方法を選べるようにすることです。
画一的な飲み会に固執するのではなく、多様な価値観に対応できる柔軟な姿勢が、現代の上司には求められています。
新しい関係構築のヒント
部下との間に新しい、そして良好な関係を築くためには、上司自身の意識改革が不可欠です。飲み会という一つの手段に頼るのではなく、日々の業務の中での関わり方を見直していきましょう。

以下に、今日から実践できる3つのヒントをご紹介します。
感謝と承認を言葉にする
「ありがとう」「助かったよ」「その視点は面白いね」など、ポジティブなフィードバックを積極的に言葉にして伝えることを意識してください。
部下は「自分は正当に評価されている」「この上司は自分のことを見てくれている」と感じ、心理的な安全性が高まります。これが信頼関係の土台となります。
部下の「個」に関心を持つ
業務スキルだけでなく、その部下がどのようなことに興味があり、何を大切にしているのかに関心を持ちましょう。ただし、プライベートに過度に踏み込むのはNGです。
1on1などの場で、「最近、何かハマっていることある?」といったオープンな質問から、相手が話したい範囲で話を聞く姿勢が大切です。相手を尊重する気持ちが伝われば、部下も心を開きやすくなります。
上司から自己開示する
完璧な上司でいようとする必要はありません。時には自分の失敗談や、仕事で悩んでいることをオープンに話すことで、部下は親近感を覚えます。
上司の人間らしい一面を見ることで、部下も自分の弱さや悩みを相談しやすくなるのです。風通しの良い関係は、上司の自己開示から始まります。
まとめ:部下が飲み会に来なくなった理由と信頼されるための神対応
いかがでしたか?部下が飲み会に来なくなると、上司としては寂しさや戸惑いを感じるかもしれません。
しかし、それは時代の変化を反映した自然な流れであり、部下の価値観を理解する絶好の機会です。
飲み会に頼るのではなく、日々の業務での感謝の言葉やランチでの対話など、新しいコミュニケーションを試みましょう。
この記事が新しいチーム作りの一助となれば幸いです。
最後に今回の記事をまとめます。

- 部下が飲み会に来ないのは価値観やライフスタイルの変化が背景にある
- プライベートな時間の尊重が現代の若手社員の大きな特徴
- 飲み会での気遣いや経済的負担が不参加の理由になることも多い
- 飲み会に行かない選択は自己投資の時間を生む賢い判断とも言える
- 時間を戦略的に使う成功者は目的のない飲み会には参加しない
- 飲み会不参加で嫌われるのではという不安を部下は抱えている
- 業務成果で評価する姿勢が部下の不安を和らげる
- 上司の古い価値観の押し付けは部下の成長を阻害する
- 自慢話や説教ばかりの上司がいる飲み会に人は集まらない
- 飲み会の強制参加はパワハラに該当するリスクが非常に高い
- 飲み会に固執せず新しいコミュニケーションの形を模索することが重要
- ランチミーティングや1on1の充実が有効な代替案となる
- 日頃からの感謝と承認の言葉が信頼関係の土台を築く
- 飲み会に頼らなくても強いチーム作りは可能である